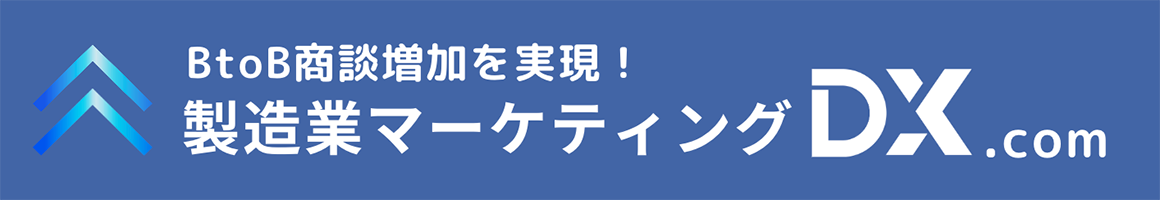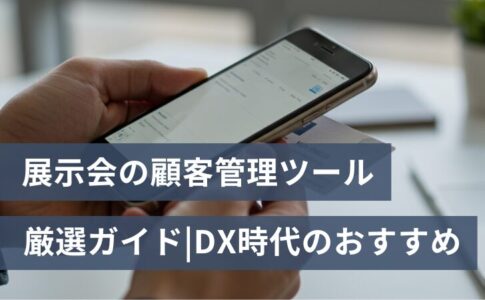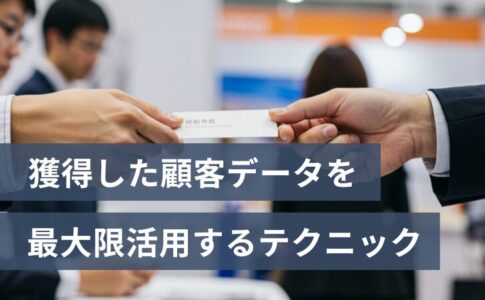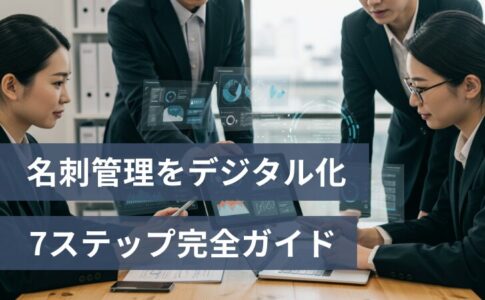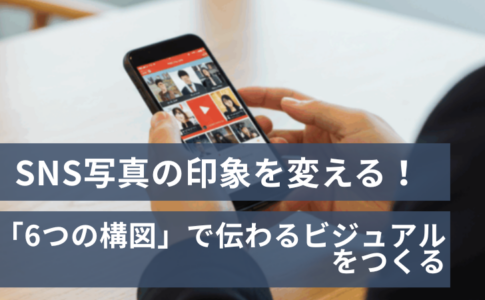展示会とYouTubeの組み合わせが、ビジネスの集客戦略として注目を集めています。従来の展示会マーケティングに動画コンテンツを融合させることで、集客効果を大幅に高められる可能性が広がっています。
展示会への出展は多くの企業にとって大きな投資です。せっかく出展するなら、最大限の成果を上げたいもの。そこで今、注目されているのがYouTubeを活用した集客戦略です。
この記事では、展示会とYouTubeを組み合わせた最新の集客手法や成功事例を紹介します。2025年の最新トレンドを踏まえながら、あなたのビジネスに役立つ実践的なノウハウをお届けします。
【目次】
展示会集客の課題とYouTube活用の可能性
展示会出展で多くの企業が直面する課題は何でしょうか。短い文章で考えてみましょう。
展示会では、ブースに立ち寄る来場者の数や質が成果を左右します。しかし、多くの企業が「思うような集客ができない」「名刺は集まっても商談につながらない」といった課題を抱えています。特に製造業などのBtoB企業にとって、展示会は重要な商談機会であるにもかかわらず、その効果を最大化できていないケースが少なくありません。

近年の展示会では、単に製品やサービスを展示するだけでは、来場者の関心を引きつけることが難しくなっています。
そこで注目されているのが、YouTubeを活用した展示会マーケティングです。YouTubeは世界最大の動画プラットフォームであり、その影響力は計り知れません。展示会とYouTubeを組み合わせることで、以下のようなメリットが期待できます:
- 展示会前の事前集客の強化
- ブースでの来場者体験の向上
- 展示会後のフォローアップ効果の最大化
- オンライン上での継続的な情報発信
特に2025年現在、コロナ禍を経てハイブリッド型の展示会が一般化する中、オンラインとオフラインを融合させた戦略の重要性がますます高まっています。
あなたは展示会の成果に満足していますか?
次のセクションでは、YouTubeを活用した具体的な展示会集客戦略について詳しく見ていきましょう。
展示会前:YouTube活用による事前集客戦略
展示会の成功は、当日だけでなく事前の集客活動にかかっています。YouTubeを活用した効果的な事前集客戦略を見ていきましょう。
展示会の数週間前から計画的に動画コンテンツを公開することで、潜在的な来場者の興味を引き、ブース訪問を促すことができます。事前集客のためのYouTube活用法として、以下の3つの方法が特に効果的です。
1. ティーザー動画の公開
ティーザー動画とは、展示会で公開予定の新製品やサービスの一部を先行して紹介する短い動画です。全てを見せるのではなく、一部だけを公開することで、「続きは展示会で」という期待感を高める効果があります。

ティーザー動画は30秒から1分程度の短い尺で、視聴者の興味を引くインパクトのある内容にすることがポイントです。「この続きが気になる」と思わせることで、展示会への来場動機を高めることができます。
2. 前回の展示会の様子を紹介する動画
過去の展示会の様子を紹介する動画は、初めて来場を検討している方にとって、具体的なイメージを持ちやすくするという効果があります。特に人気のあったブースの様子や、セミナーの一部、来場者の反応などを含めることで、「自分も行ってみたい」という気持ちを喚起できます。
実際に、ある製造業の企業では、前回の展示会の様子をまとめた5分程度の動画を公開したところ、新規来場者が前回比で30%増加したという事例もあります。
3. 出展者・登壇者からのメッセージ動画
展示会に出展する企業の代表者や、セミナーの登壇者からのメッセージ動画も効果的です。顔が見える形で展示会の見どころや価値を伝えることで、信頼感と期待感を高めることができます。
特に業界の著名人や専門家が登場する動画は拡散されやすく、通常よりも広い層に情報が届く可能性があります。メッセージ動画は1〜2分程度の短い尺で、具体的な価値提案を含めることがポイントです。
これらの動画を効果的に活用するためには、以下の点に注意しましょう:
- 公開タイミングは展示会の2〜4週間前が最適
- SNSやメールマガジンと連動させて拡散する
- 動画の説明欄に展示会の詳細情報やブース番号を記載する
- 視聴者が次のアクションを取りやすいよう、明確なCTAを設定する
あなたの展示会準備は、どのくらい前から始めていますか?
事前の集客活動に力を入れることで、当日のブース訪問者数を大幅に増やすことが可能です。次は、展示会当日のYouTube活用法について見ていきましょう。
展示会当日:ブースでのYouTube活用テクニック
展示会当日、あなたのブースを目立たせるためにYouTubeをどう活用すればよいのでしょうか?
展示会場には多くのブースが並び、来場者の注目を集めるのは容易ではありません。そこで効果を発揮するのが、ブース内でのYouTube動画の戦略的な活用です。来場者の目を引き、足を止めてもらうための具体的なテクニックを紹介します。
1. 集客動画のループ再生
ブースの目立つ位置に大型ディスプレイを設置し、注目を集める動画をループ再生することで、遠くからでも来場者の視線を引きつけることができます。この集客動画は音声よりも視覚的なインパクトを重視し、10〜30秒程度の短い尺で繰り返し再生するのが効果的です。

ある工作機械メーカーでは、製品の動作シーンをスローモーションで美しく映した動画をループ再生したところ、通常の静態展示に比べてブース訪問者が2倍に増加したという事例があります。
2. インタラクティブなデモンストレーション
製品やサービスの使い方をYouTube動画で分かりやすく解説し、来場者が実際に体験できるコーナーを設けることで、深い理解と印象付けが可能になります。動画と実体験を組み合わせることで、情報の定着率が大幅に向上します。
特に複雑な製品や、一見しただけでは価値が伝わりにくいサービスの場合、動画による解説は非常に効果的です。来場者は自分のペースで情報を得ることができ、その後のスタッフとの会話もスムーズになります。
3. リアルタイム配信の活用
展示会の様子をYouTubeでライブ配信することで、会場に来られなかった人々にもリアルタイムで情報を届けることができます。特に注目の新製品発表やセミナーなどをライブ配信することで、オンライン上での拡散効果も期待できます。
2025年現在、多くの展示会がハイブリッド形式を採用しており、リアルタイム配信は標準的なサービスになりつつあります。自社のチャンネルでライブ配信を行うことで、より多くの視聴者にリーチすることが可能です。
私は以前、ある展示会でブース内のセミナーをライブ配信したことがあります。当日の来場者は30名程度でしたが、オンライン視聴者は200名を超え、後日のアーカイブ視聴も含めると500名以上に情報を届けることができました。
展示会当日のYouTube活用では、以下の点に注意すると効果が高まります:
- Wi-Fi環境を事前に確認し、必要に応じてポケットWi-Fiなどのバックアップを用意する
- 動画は音声がなくても内容が伝わるよう工夫する(会場は騒がしいため)
- QRコードなどを用意し、その場で自社チャンネルの登録を促す
- 来場者の許可を得た上で、インタビュー動画などのコンテンツを作成する
あなたは展示会ブースで、どのような工夫をしていますか?
次のセクションでは、展示会後のフォローアップにYouTubeをどう活用するかについて解説します。
展示会後:YouTube活用によるフォローアップ戦略
展示会が終わった後が本当の勝負です。せっかく集めた名刺や接点をビジネスチャンスに変えるために、YouTubeを活用したフォローアップ戦略を見ていきましょう。
多くの企業が展示会後のフォローに課題を抱えています。名刺は集まったものの、その後の商談につながらないというケースは珍しくありません。YouTubeを活用したフォローアップは、従来の電話やメールよりも印象に残りやすく、商談化率を高める効果があります。
1. お礼動画の送付
展示会でブースに立ち寄ってくれた方々に向けた「お礼動画」を作成し、メールなどで送付する方法が効果的です。一般的なテキストメールよりも、担当者が直接感謝の言葉を伝える動画の方が、人間味があり印象に残ります。
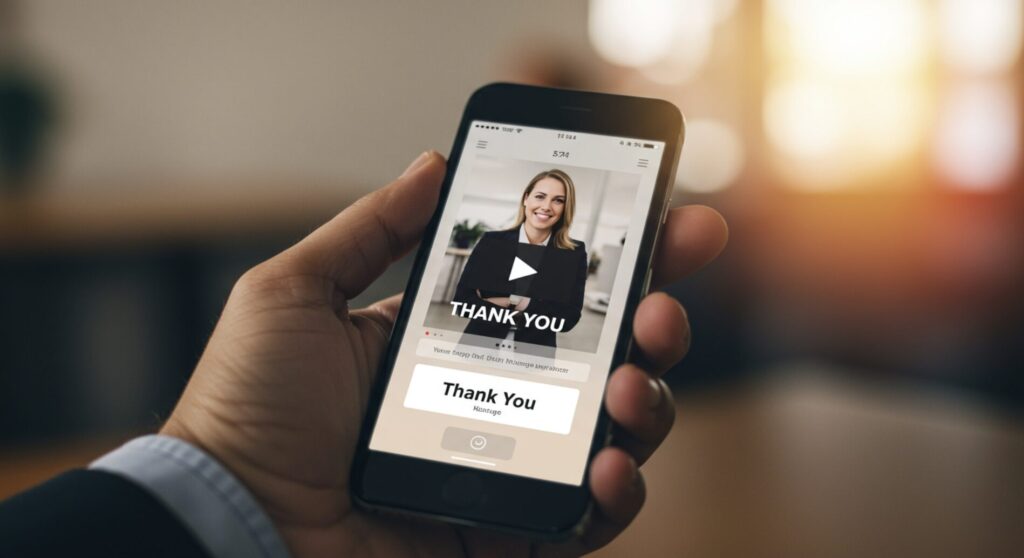
お礼動画は1分程度の短い尺で、以下の要素を含めると効果的です:
- 具体的な感謝の言葉(可能であれば来場者の名前に言及)
- 展示会での対話内容に触れる
- 追加情報の提供
- 次のステップの提案(資料送付、デモ、訪問など)
DIXIが提供する「展示会×営業DX支援パッケージ」では、このようなフォローアップを効率的に行うサポートも含まれています。展示会で獲得した名刺には、継続的に情報発信を行うことで、展示会期間終了後も商談獲得につなげることが可能です。
2. 展示会アーカイブ動画の作成
展示会の様子をまとめたアーカイブ動画を作成し、来場できなかった人や、もう一度内容を確認したい人向けに公開する方法も効果的です。特にセミナーや製品デモンストレーションの内容は、動画として残しておくことで長期的な資産になります。
アーカイブ動画は以下のような構成にすると見やすくなります:
- 展示会の概要(日時、場所、テーマなど)
- 自社ブースの様子
- 製品・サービスの紹介
- セミナーや講演のハイライト
- 来場者の声
- 次回展示会の予告
これらの動画は自社サイトやSNSでも共有し、展示会に参加できなかった潜在顧客へのアプローチにも活用できます。
3. フォローアップセミナーのオンライン開催
展示会後に関連テーマでのオンラインセミナーをYouTubeで開催することで、興味を持った層との接点を維持・強化できます。展示会で得た質問や関心事をもとにテーマを設定すれば、参加者の満足度も高まります。
オンラインセミナーは、以下のようなメリットがあります:
- 地理的制約なく参加できる
- 録画して後から視聴することも可能
- チャット機能を使った質疑応答ができる
- 参加者の行動(視聴時間、コメントなど)を分析できる
展示会後のフォローアップでは、タイミングが重要です。展示会終了後1週間以内に最初のコンタクトを取り、その後も定期的に情報を提供することで、見込み客との関係を深めていくことができます。
展示会で獲得した名刺の山を眺めて「さて、どうしよう」と悩んだことはありませんか?
YouTubeを活用したフォローアップ戦略を導入することで、展示会投資の回収率を大幅に高めることができます。次のセクションでは、具体的な成功事例を紹介します。
展示会×YouTube活用の成功事例
理論だけでなく実践例を見ることで、展示会×YouTubeの可能性がより具体的に理解できます。ここでは、実際に成功を収めた企業の事例を紹介します。
1. 製造業メーカーの事例 – 名刺獲得数410%達成
株式会社東洋新薬のマーケティング室では、展示会プロモーション支援を導入し、YouTubeを含むデジタル戦略を展開しました。その結果、目標を大きく上回る新規見込み客との接点を作ることに成功し、名刺獲得数は過去最多を記録しました。
同社の担当者は「コロナ禍の展示会でしたが、名刺の獲得数は当社が過去出展した展示会の中で過去最多の数でした」と成果を語っています。
成功のポイントは、展示会前にYouTubeで製品紹介動画を公開し、メールマガジンやSNSで拡散したこと。さらに展示会当日はブースでのデモンストレーション動画をループ再生し、来場者の注目を集めました。
2. テックスタートアップの事例 – 商談化率3倍に
テレワーク時代のリアルタイム情報共有ツール「flouu」を開発・販売するプライズ株式会社では、展示会×YouTubeの活用により、商談化率が従来の3倍になったと報告しています。

同社の代表取締役CEOである内田氏は「2年前の出展時は自社で全て対応しました。アルバイトを雇い、チラシを配り、自分達でフォローコールも実施しました。結果、フォローコールの時間が確保できなかったり、電話でのコミュニケーション技術の不足によりリードからの商談化数も満足のいくものではありませんでした」と以前の課題を振り返っています。
そこで同社は、展示会の様子をYouTubeでライブ配信するとともに、展示会後のフォローアップにも動画コンテンツを活用。具体的には、展示会で収集した質問や関心事をもとにしたミニセミナー動画を制作し、見込み客に送付しました。
その結果、「1回の出展ごとに何十件と商談化できている」と大きな成果を上げています。
3. 住宅メーカーの事例 – YouTubeで展示場を代替
ある住宅メーカーでは、「YouTubeで展示場」というコンセプトで、実際の展示場に行かなくても住宅の魅力が伝わるよう、詳細な3D動画コンテンツを制作しました。
特に注目すべきは、このアプローチが「広告費0円ですぐに始められる」という点です。モデルハウスの建設・維持にかかるコストと比較して、YouTube動画の制作・公開は大幅にコストを抑えることができます。
これらの成功事例から学べるポイントは以下の通りです:
- 展示会前・中・後の一貫した戦略が重要
- 単なる製品紹介ではなく、視聴者の課題解決に焦点を当てた内容にする
- 専門的なノウハウを持つパートナーと協力することで効果が高まる
- 継続的なコンテンツ発信が長期的な成果につながる
展示会とYouTubeを組み合わせた戦略は、2025年現在、多くの企業で標準的なアプローチになりつつあります。次のセクションでは、効果的な展示会×YouTube戦略を立てるためのステップを解説します。
展示会×YouTube戦略の立て方と実践ポイント
展示会とYouTubeを効果的に組み合わせるための具体的な戦略立案方法と実践ポイントを紹介します。
成功する展示会×YouTube戦略には、綿密な計画と準備が不可欠です。以下の5つのステップに沿って戦略を立てることで、効果的な展開が可能になります。
1. 目標設定と指標の明確化
まず最初に、展示会出展の目的と、YouTubeを活用することで達成したい具体的な目標を明確にします。例えば以下のような目標が考えられます:
- ブース来場者数の増加(前回比○○%アップ)
- 名刺獲得数の増加(目標○○枚)
- 商談化率の向上(○○%以上)
- YouTubeチャンネル登録者数の増加(○○人増)
- 認知度向上(アンケートによる測定)
目標を数値化することで、後の効果測定がしやすくなります。また、各指標の測定方法も事前に決めておくことが重要です。
2. ターゲットオーディエンスの特定
効果的なコンテンツを作るためには、ターゲットとなる視聴者・来場者を具体的に特定することが重要です。以下のような点を明確にしましょう:
- 業種・職種
- 役職・決裁権の有無
- 年齢層・性別
- 抱えている課題や関心事
- 情報収集の習慣(よく見るメディアなど)
ターゲットが明確になれば、その層に響くコンテンツの方向性も見えてきます。
3. コンテンツ計画の策定
展示会の前・中・後に分けて、どのようなコンテンツをいつ公開するかを計画します。以下は基本的なコンテンツ計画の例です:
- 展示会2ヶ月前:展示会告知動画
- 展示会1ヶ月前:製品・サービスのティーザー動画
- 展示会2週間前:登壇者・出展者インタビュー
- 展示会当日:ライブ配信、ブースの様子
- 展示会後1週間以内:お礼動画、ハイライト動画
- 展示会後2〜4週間:フォローアップセミナー、詳細解説動画
各動画の尺や構成、訴求ポイントも事前に決めておくと、制作がスムーズになります。
4. 制作・配信体制の構築
質の高い動画コンテンツを継続的に制作・配信するための体制を整えます。以下の点を検討しましょう:
- 社内で制作するか、外部に依頼するか
- 必要な機材(カメラ、マイク、照明など)
- 編集ソフトや配信ツール
- 担当者の役割分担
- スケジュール管理の方法
DIXIが提供する「展示会×営業DX支援パッケージ」では、展示会場でのブース毎の出展内容を動画で撮影し、展示会サイトやYouTubeにアップするサービスも含まれています。自社でのリソースが限られている場合は、このような専門サービスの活用も検討する価値があります。
5. 効果測定と改善
展開した戦略の効果を測定し、次回に向けた改善点を洗い出します。YouTubeの分析機能を活用すれば、以下のような指標が測定できます:
- 視聴回数と視聴者層
- 視聴維持率(どこまで見られているか)
- エンゲージメント(いいね、コメント、共有)
- トラフィックソース(どこから視聴しているか)
- コンバージョン(リンククリック、問い合わせなど)
これらのデータを分析し、次回の展示会に向けた改善策を立てることで、継続的な成果向上が期待できます。
展示会×YouTube戦略を成功させるための実践ポイントとして、以下の点も押さえておきましょう:
- 一貫したブランディングを心がける(ロゴ、色使い、BGM等)
- 最初の5秒で視聴者の興味を引く工夫をする
- 字幕を付けて音声がなくても内容が伝わるようにする
- SEO対策を意識したタイトルや説明文を設定する
- 視聴者に次のアクションを促す明確なCTAを入れる
あなたの会社では、展示会マーケティングにどのくらいの予算を割いていますか?
展示会×YouTube戦略を適切に実行することで、従来の展示会マーケティングよりも低コストで高い効果を得ることが可能です。次のセクションでは、この戦略を導入する際の注意点について解説します。
展示会×YouTube戦略導入の注意点と課題解決法
展示会×YouTube戦略を導入する際に直面しがちな課題と、その解決法について解説します。
どんな戦略にも課題はつきものです。ここでは、よくある課題とその対処法を紹介することで、スムーズな導入をサポートします。
1. リソース不足への対応
多くの企業が直面するのが、動画制作や運用のためのリソース(人材・時間・予算)不足の問題です。特に中小企業では、専任の担当者を置くことが難しいケースも少なくありません。
この課題に対しては、以下のような解決策が考えられます:
- 外部の専門サービスの活用(DIXIの「展示会×営業DX支援パッケージ」など)
- スマートフォンやタブレットを活用した簡易的な動画制作
- テンプレート化できる部分は再利用して効率化
- 社内の若手社員や動画制作に興味のある社員の活用
リソースが限られている場合は、すべてを完璧にしようとするのではなく、重点的に力を入れる部分を絞ることも大切です。
2. コンテンツの質と継続性の確保
一時的に良質なコンテンツを作っても、継続的に発信できなければ効果は限定的です。また、質の低いコンテンツは逆効果になる可能性もあります。
この課題に対しては、以下のような解決策が考えられます:
- 年間コンテンツカレンダーの作成による計画的な運用
- 制作プロセスの標準化(企画→撮影→編集→公開のフロー確立)
- 社内の複数部門を巻き込んだコンテンツ制作体制の構築
- 既存コンテンツのリサイクル・リパーパス(目的変更)
特に重要なのは、無理のない頻度でコンテンツを発信し続けることです。質と量のバランスを考慮した現実的な計画を立てましょう。
3. 効果測定と投資対効果の証明
展示会×YouTube戦略の効果を適切に測定し、経営層に投資対効果を示すことが難しいと感じる担当者も多いでしょう。
この課題に対しては、以下のような解決策が考えられます:
- KPIの明確化と定期的な測定・報告の仕組み化
- YouTubeアナリティクスとCRMの連携による顧客行動の追跡
- アンケートによる来場者の情報源調査(「どこで知りましたか?」)
- A/Bテストによる効果検証(動画あり/なしの比較など)
数値化できる指標を設定し、継続的に測定することで、戦略の効果を客観的に示すことができます。
4. 競合との差別化
多くの企業がYouTubeを活用し始めている中、いかに競合と差別化するかも重要な課題です。
この課題に対しては、以下のような解決策が考えられます:
- 自社ならではの専門知識や独自の視点を前面に出す
- 社員の個性や企業文化を活かしたコンテンツ作り
- 顧客の声や成功事例を積極的に取り入れる
- 新しい表現方法や技術の積極的な採用(360度動画、インタラクティブ動画など)
差別化のポイントは「誰でもできること」ではなく、「自社だからこそできること」を見つけ出すことです。
展示会×YouTube戦略の導入に不安を感じていませんか?
これらの課題は、多くの企業が経験するものです。一度にすべてを解決しようとするのではなく、段階的に取り組むことで、持続可能な戦略を構築することができます。
まとめ:展示会×YouTubeで集客を倍増させるための行動計画
ここまで展示会とYouTubeを組み合わせた集客戦略について詳しく見てきました。最後に、実際に行動に移すための具体的なステップをまとめます。
展示会×YouTube戦略は、適切に実行すれば集客効果を大幅に高められる可能性を秘めています。2025年の現在、デジタルとリアルを融合させたハイブリッドなアプローチがますます重要になっています。
まず、展示会前・中・後の各フェーズで実施すべきアクションを整理しましょう:
展示会前(2〜8週間前)
- 目標設定と戦略立案
- ティーザー動画の制作・公開
- 過去の展示会の様子や出展者メッセージの配信
- SNSやメールマガジンと連動した拡散
展示会当日
- ブースでの集客動画のループ再生
- インタラクティブなデモンストレーション
- リアルタイム配信の実施
- 来場者インタビューや反応の記録
展示会後(1〜4週間後)
- お礼動画の送付
- 展示会アーカイブ動画の公開
- フォローアップセミナーの開催
- 効果測定と次回への改善点の洗い出し
これらのアクションを実行するにあたり、以下の3つのポイントを押さえることが重要です:
1. 一貫した戦略の構築:展示会前・中・後で一貫したメッセージとブランディングを維持し、顧客体験の連続性を確保しましょう。
2. 顧客中心のコンテンツ設計:自社の製品・サービスの特徴だけでなく、顧客の課題解決や価値提供に焦点を当てたコンテンツを心がけましょう。
3. 継続的な改善サイクルの確立:データに基づいて効果を測定し、次回の展示会に向けて継続的に戦略を改善していくプロセスを確立しましょう。
展示会×YouTube戦略の導入は、一朝一夕にできるものではありません。しかし、小さな一歩から始めて徐々に拡大していくことで、大きな成果につなげることができます。
展示会の名刺獲得で終わらせず、効果的なフォローアップまで含めた総合的な戦略を実践することで、展示会投資の回収率を最大化しましょう。
DIXIの「展示会×営業DX支援パッケージ」は、展示会での集客から名刺獲得、一次商談、顧客管理、展示会後の顧客育成までをワンストップでサポートします。展示会出展の効果を最大化し、確度の高い商談機会を創出したい企業様は、ぜひご検討ください。
展示会の名刺獲得で終わらせない!製造業のための『展示会×営業DX』完全攻略セミナーで、さらに詳しい情報や最新の成功事例をご紹介しています。