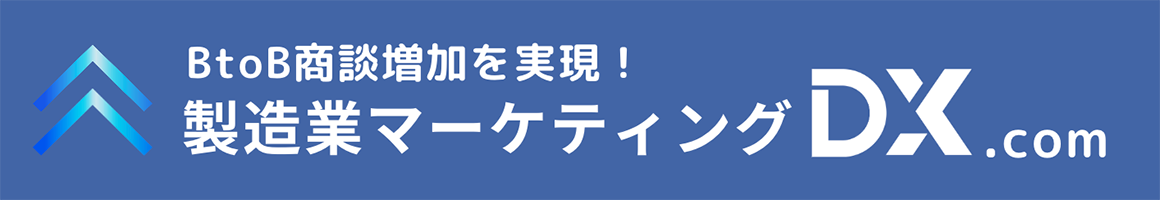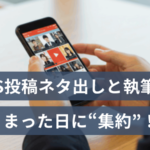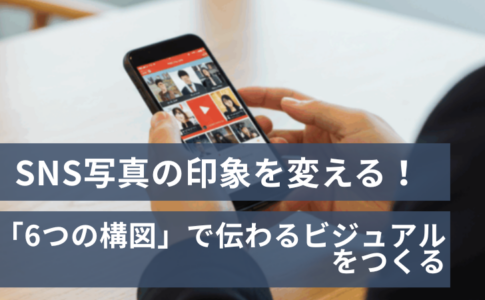【目次】
DXとは、何なのか
近年、どの業界でも「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を耳にするようになりました。
展示会やセミナーではDX事例が次々と紹介され、補助金のテーマにも「DX」の文字が頻繁に登場します。
- 「うちの業務はアナログだらけで、どこから手をつければいいかわからない」
- 「AIで何が業務効率化されるのか、いまいちピンとこない」
- 「何のツールを導入すればいいのか、判断がつかない」
私の結論として、DXとは「デジタルを活用して、あらゆる業務をデータ化し、再現性を生み出すこと」だと考えています。
単に紙をデジタルに置き換えることではありません。
“経営の仕組み・業務の流れ・顧客との関係性”をデジタルで可視化・構造化し、再現性のある業務へと変革する取り組み。
これが、DXと考えています。

なぜ「デジタル化」とは違うのか
経済産業省の定義では、DXは次のように説明されています。「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、
製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、
業務そのものや組織・企業文化を変革すること。」
つまり、DX=IT導入ではありません。
本質は「変革(トランスフォーメーション)」にあります。
たとえば、
・紙の伝票をExcelにする
➡「デジタル化」
・Excelで集めたデータをもとに、営業活動を見直す
➡「業務改善」
・さらに、そのデータを顧客提案や商品開発に活かし、会社の稼ぎ方を変える
➡「DX」
このように段階があります。
デジタル化はDXの入り口であり、DXのゴールではありません。
DXを進める順番:順序を間違えないことが大切
DX推進には「正しい順番」があります。
多くの企業が失敗するのは、この順番を飛ばしてしまうからです。
「ツール導入ありき」ではなく、
「業務の背景」と「目的」から出発すること。
ここが最も重要なポイントです。
① 業務の背景・目的を整理する
—経営レベルと業務レベルの両面から考える—
DXの第一歩は、「なぜ変えたいのか」を言語化すること。
ここを曖昧にしたまま「システム・ツールを入れたい」と進めると、現場が混乱します。
たとえば、経営レベルでは、「利益率を上げたい」「属人化を解消したい」「顧客対応を標準化したい」といった目的があります。
一方で、業務レベルでは、「見積作成の手間を減らしたい」「紙伝票をやめたい」「在庫の数をリアルタイムで把握したい」といった課題があるはずです。
これらを「経営レベル」と「業務レベル」に分けて整理し一貫性を通すことで、DXの目的が明確になります。
両レベルの目的に一貫性があれば、DXに向けた施策や対象領域の選定においても、自然と「筋の通った判断」ができるようになります。
② 現行業務の把握と改善ポイントの発見
—「どこからやるか」を決めるだけでもDXの第一歩—
DXを進めるには、まず現行業務を見える化する必要があります。
「どの業務に、どれだけの手間がかかっているのか?」
「誰が、どんな判断をしているのか?」
このような実態を書き出すところから始めます。
そして、改善ポイントを洗い出す際のコツは、
「無理にトレンドに乗らないこと」です。
「顧客管理システム(CRM)を導入したほうがいい」
「AIで何かに導入しよう」
こうした流行りのテクノロジーも魅力的ですが、
もし社内の情報共有や業務プロセスが整理されていなければ、ツールは宝の持ち腐れになります。
大事なのは、「自社がやりたいところから始める」こと。
顧客管理からでも、在庫管理からでも、営業の見積からでも構いません。
やりたいところ、改善したいところを一つ決め、
「業務の流れ」と「データの流れ」をセットで整理する。
これだけでも、DXの地盤が整いはじめます。
③ デジタル化
—アナログをデジタルに置き換える段階—
次に、具体的に「デジタル化」を進めます。
ここでは、紙や口頭でやっていたことを、
デジタルツールやアプリに置き換えていきます。
たとえば、
・紙の日報 → スマホ入力フォーム(Googleフォーム)
・Excel共有 → クラウドDB(Airtableなどのスプレッドシート的DBツール)
・手作業の報告 → 自動通知(Google Apps Scriptなどの自動化スクリプト)
この段階では「データが貯まる仕組みを作る」ことが目的です。
つまり、「人の記憶や紙に依存しない状態」をつくること。
ここまで来ると、「見える化」が進みます。
誰が何をしているのか、どこで止まっているのか、
経営者が数字で把握できるようになります。
ただし、ここで終わってしまうと「デジタル化止まり」です。
④ DX化
—データを活用して、経営や業務を“変える”段階—
DX化の段階では、「集めたデータをどう活かすか」がテーマになります。
・過去の受注データから「次の受注確率」を予測
・営業別の成約率を見える化して、育成方針を変える
・在庫と生産計画を連携させ、ムダな仕入れを削減する
こうした取り組みは、単に効率を上げるだけでなく、
会社の稼ぎ方・判断の仕組みそのものを変えることにつながります。
つまり、DX化とは「データが意思決定を支える会社になる」ことです。
これを実現すると、経営者の経験や勘に頼らず、
“再現性のある成果”を出す仕組みが作れます。
たとえば、
「売上が落ちたら、何を見直すべきか」が数字でわかる。
「誰がボトルネックになっているのか」が可視化される。
「次に打つべき一手」が、現場と経営の両方で共有できる。
ここまで来ると、単なるIT導入ではなく、
経営そのものがデジタルを前提とした仕組みに変わっていきます。
DXのゴールは「デジタルで回る経営体制」
DXの最終的な目的は、
“データを使って利益を上げ続ける仕組み(再現性)をつくること”です。
つまり、DXのゴールは「仕組み」そのもの。
その仕組みが社員の行動を変え、
行動の積み重ねが会社の競争力を高めていきます。
そして、こうした変化を少しずつ積み上げることが、
結果的に大きな経営改革につながっていきます。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
現在、DIXIでは、企業の業務改善を支援する取り組みを行っております。
業務課題の整理から、ツールに頼らない柔軟性のあるシステム・アプリケーションの開発まで、幅広く対応しています。
もし少しでも「相談してみようかな」と思われたら、ぜひ下記のリンクからお気軽にご連絡ください。
あなたの想いや課題に寄り添いながら、最適な方法をご提案させていただきます。