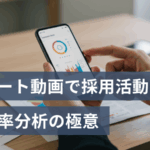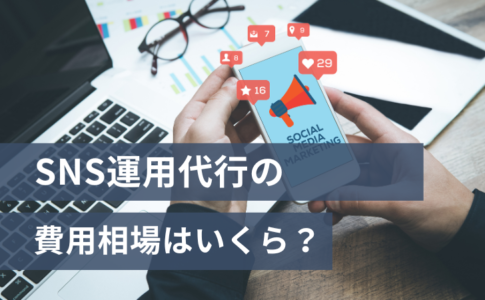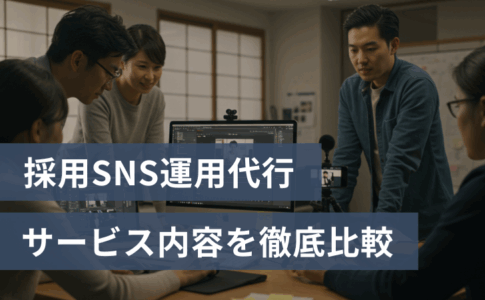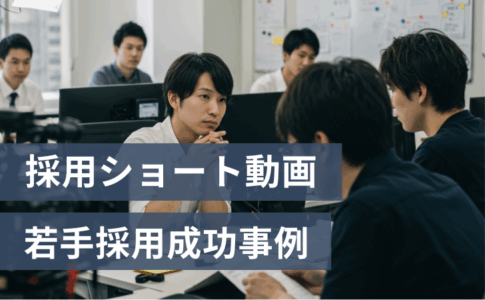BtoB企業が採用SNSを運用する意義と現状
採用市場の競争が激化する中、BtoB企業においても採用SNS運用の重要性が高まっています。特に若手人材の獲得において、従来の採用手法だけでは効果が限定的になりつつあるのが現状です。
「うちはBtoB企業だからSNSは必要ない」と考えていませんか?
実は、帝国データバンクの調査によると、製造業や卸売業といったBtoB事業でも約30~40%の企業がすでにSNSを活用しています。その中でも採用活動にSNSを取り入れる企業が急増しているのです。
私自身、ある製造業のクライアント企業でSNS運用支援を行った際、最初は「BtoB企業なのにSNSなんて…」と懐疑的だった採用担当者が、3ヶ月後には「こんなに反応があるとは思わなかった」と驚いていました。若手エンジニア応募者の約40%がSNSをきっかけに興味を持ったと回答したのです。
BtoB企業の採用SNS運用には、以下のような明確なメリットがあります:
- 自社の認知度アップにつながる
- 社風など自社の魅力を多方面から発信できる
- 採用コストを抑えられる
- 若年層へのアプローチが強化できる
- 企業ブランディングの構築に寄与する
しかし、これらのメリットを最大化するためには、適切な社内体制の構築が不可欠です。多くのBtoB企業が採用SNS運用を始めるものの、継続できずに挫折してしまうケースが少なくありません。
本記事では、BtoB企業が採用SNSを効果的に運用するための社内体制構築方法について、具体的な成功事例とともに解説します。

BtoB企業の採用SNS運用における課題
BtoB企業が採用SNSを運用する際には、BtoC企業とは異なる独自の課題が存在します。これらの課題を理解することが、効果的な社内体制構築の第一歩となります。
まず、最も大きな課題は「リソースとノウハウの不足」です。
製造業や運送業などのBtoB企業では、SNSマーケティングの専門知識を持つ人材が社内に少なく、採用担当者が兼任で運用するケースが多いのが現状です。そのため、効果的な投稿内容や運用方法がわからず、継続的な運用が難しくなってしまいます。
次に「ネタの枯渇と投稿内容の問題」があります。BtoB企業では「何を投稿すべきか」という悩みを抱えがちです。特に製造業などでは、製品やサービスが一般消費者向けではないため、採用目的でどのような内容を発信すべきか迷ってしまうことが少なくありません。
ある機械製造業のマーケティング担当者は、「最初の1ヶ月は意気込んで投稿していたが、その後はネタ切れになってしまった」と打ち明けていました。結局、更新頻度が落ち、フォロワーの減少につながったそうです。
また、「否定的反応・炎上リスクへの過敏さ」も見逃せない課題です。
BtoB企業は一般的に保守的な企業文化を持つ傾向があり、SNSでの発信に対して慎重になりがちです。「変なことを投稿して会社の評判を落としたらどうしよう」という不安から、承認プロセスが複雑化し、タイムリーな投稿ができなくなるケースもあります。
さらに、「効果測定の難しさ」も大きな課題です。SNS運用の成果が採用にどれだけ貢献しているのか、数値化して経営層に説明することが難しく、結果として予算や人員の確保が困難になることがあります。
これらの課題を克服するためには、単にSNSアカウントを開設するだけでなく、継続的に運用できる社内体制の構築が不可欠なのです。

効果的な採用SNS運用のための5つの社内体制
BtoB企業が採用SNSを効果的に運用するためには、以下の5つの社内体制を整備することが重要です。これらの体制は、先述した課題を解決し、持続可能なSNS運用を実現するための基盤となります。
1. 経営陣の理解と関与
採用SNS運用を成功させるためには、まず経営陣の理解と支援を得ることが不可欠です。SNS運用は短期的な成果が見えにくいため、経営陣が中長期的な視点で取り組む姿勢を持つことが重要です。
具体的には、以下のような取り組みが効果的です:
- 経営会議でSNS運用の目的と期待効果を明確に説明する
- 他社の成功事例を具体的な数字とともに提示する
- 四半期ごとにSNS運用の成果報告会を実施する
- 可能であれば経営陣自身がSNSに登場する機会を作る
ある建設機械メーカーでは、社長自らがInstagramに登場し、「社長の一日」というコンテンツを定期的に投稿しています。このコンテンツは若手応募者からの反響が特に高く、「経営者の人柄が伝わってきて親近感が湧いた」という声が多数寄せられているそうです。
2. 社内の協力体制とネタ共有文化
SNS運用を担当者一人に任せきりにせず、全社的な協力体制を構築することが重要です。特に「ネタ切れ」の問題を解決するためには、社内各部署からの情報提供が欠かせません。
効果的な協力体制づくりには、以下のような施策が有効です:
- 各部署に「SNSコンテンツ提供担当」を設置する
- 社内ポータルサイトに「SNSネタ投稿フォーム」を設置する
- 月1回の「SNSコンテンツ会議」を開催する
- 投稿が採用された社員を表彰する制度を設ける
- 社員が主役となるコンテンツシリーズを企画する
製造業のA社では、「#うちの会社の〇〇さん」というハッシュタグを作り、毎週異なる部署の社員を紹介するコンテンツを展開しています。これにより、社員のSNS参加意識が高まり、自発的に「次は〇〇部の△△さんを紹介したい」という声が上がるようになったそうです。
社内の協力体制が整うと、SNS運用担当者の負担が軽減されるだけでなく、多様な視点からのコンテンツが生まれ、投稿の質と量の両方が向上します。
3. 明文化されたSNSポリシー(投稿ルール)
BtoB企業が抱える「炎上リスクへの不安」を解消するためには、明確なSNSポリシーを策定することが重要です。ポリシーがあることで、担当者は安心して投稿できるようになり、承認プロセスもスムーズになります。
SNSポリシーには、以下のような項目を含めるとよいでしょう:
- 投稿可能な内容と禁止事項の明確化
- 写真・動画撮影時の注意点(機密情報、肖像権など)
- コメント対応のガイドライン
- クライズ発生時の対応フロー
- 投稿の承認プロセス
どうですか?このようなポリシーがあれば、担当者も安心して投稿できますよね?
ある精密機器メーカーでは、SNSポリシーを策定したことで、それまで複雑だった承認プロセスが簡略化され、投稿から公開までの時間が平均3日から1日に短縮されたそうです。結果として、タイムリーな投稿が可能になり、エンゲージメント率が1.5倍に向上したとのことです。

4. 担当者の適正と育成
採用SNS運用を担当する人材の選定と育成も重要なポイントです。「誰でもできる」と考えて安易に若手社員に任せるケースもありますが、効果的な運用のためには適切な人選と継続的な育成が必要です。
担当者に求められる主な資質は以下の通りです:
- SNSの基本的な知識と利用経験
- 自社の魅力や価値観を理解している
- 文章力・コミュニケーション能力がある
- 写真・動画の基本的な撮影・編集スキルを持つ
- データ分析の基礎知識がある
これらすべてを備えた人材を見つけるのは難しいかもしれません。そこで重要なのが、担当者の継続的な育成です。
ある機械部品メーカーでは、SNS担当者に対して四半期ごとに外部研修の機会を提供しています。また、同業他社のSNS担当者との交流会を定期的に開催し、ノウハウの共有を図っているそうです。その結果、担当者のスキルアップだけでなく、モチベーション維持にも効果があったと報告されています。
また、複数名でチームを組んで運用する体制も効果的です。例えば、戦略立案担当、コンテンツ制作担当、コミュニティ管理担当など、役割を分担することで、一人あたりの負担を減らしつつ、専門性を高めることができます。
5. 効果測定とフィードバックサイクル(PDCA)
採用SNS運用の効果を可視化し、継続的に改善していくためのPDCAサイクルを確立することも重要です。特にBtoB企業では、SNS運用と採用成果の因果関係が見えにくいため、適切な指標設定と定期的な効果測定が欠かせません。
効果測定のポイントは以下の通りです:
- KPI(重要業績評価指標)の明確化
- 定量指標と定性指標の両方を設定
- 月次・四半期・年次の各レベルでの振り返り
- 採用プロセスにおけるSNSの貢献度測定
- 投稿内容とエンゲージメント率の相関分析
具体的なKPI例としては、フォロワー数、エンゲージメント率(いいね・コメント・シェア数)、リーチ数などの基本指標に加え、採用関連では「SNSをきっかけとした応募数」「SNS経由応募者の選考通過率」「SNS経由入社者の定着率」などが挙げられます。
電子部品メーカーのB社では、応募フォームに「当社を知ったきっかけ」という項目を設け、SNSの効果測定を行っています。その結果、Instagram経由の応募者は書類選考通過率が平均より15%高く、最終的な入社率も高いことが判明。この数字を経営陣に報告することで、SNS運用の予算増額につながったそうです。

BtoB企業の採用SNS運用成功事例
実際にBtoB企業が採用SNSを効果的に運用し、成果を上げている事例を見ていきましょう。これらの事例から、社内体制構築のヒントを得ることができます。
製造業:フジ産業株式会社の事例
機械製造業のフジ産業株式会社は、Instagramを活用した採用ブランディングで成功を収めています。同社は「親しみやすさ」をコンセプトに、工場で働く社員の日常や製造過程の様子を積極的に発信。特に若手社員が中心となって撮影・編集を行うことで、同世代の求職者に響くコンテンツを生み出しています。
社内体制の特徴は、「SNSアンバサダー制度」の導入です。各部署から1名ずつ「SNSアンバサダー」を選出し、月に1回のミーティングでコンテンツのアイデア出しや撮影協力を行っています。これにより、担当者一人では収集できない多様なネタを継続的に確保することに成功しています。
結果として、採用SNS運用開始から1年で、エンジニア職の応募数が前年比150%に増加。特に20代の応募者が大幅に増えたとのことです。採用コストも従来の求人広告費と比較して約30%削減できたそうです。
運送業:三陽工業の事例
町工場からスタートした三陽工業は、TikTokを活用した採用活動で注目を集めています。ドライバー不足が深刻な運送業界において、若手ドライバーの採用に苦戦していた同社は、TikTokでの情報発信を開始。「トラックドライバーあるある」や「知られざるドライバーの仕事」といったテーマで、短尺動画を定期的に投稿しています。
社内体制の特徴は、「現場主導型」の運用スタイルです。マーケティング部門ではなく、実際にドライバーとして働く社員が中心となってコンテンツを企画・制作。本社は最小限のサポートと承認のみを行い、現場の「リアル」を最大限に活かした投稿を実現しています。
私が特に印象的だったのは、あるベテランドライバーの方が語った言葉です。
「最初はSNSなんて恥ずかしいと思ったけど、自分の仕事を誇りを持って紹介できるようになって嬉しい。若い子から『動画見ました!』って声をかけられると、やりがいを感じますね」
この事例からわかるのは、SNS運用は単なる採用ツールではなく、社員のエンゲージメント向上にも寄与するということです。同社では、SNS運用開始後、社員の離職率も低下したと報告されています。
BtoB企業:ナブテスコ株式会社の事例
BtoB大企業であるナブテスコ株式会社は、キャラクター運用による情報発信で成功を収めています。同社は一般消費者には馴染みが薄い製品を扱っていますが、公式キャラクター「ナブテスコットくん」を活用し、複雑な技術や製品を親しみやすく紹介しています。
社内体制の特徴は、「クロスファンクショナルチーム」の編成です。広報・人事・技術部門から選抜されたメンバーでSNS運用チームを構成し、それぞれの専門性を活かしたコンテンツ制作を行っています。特に技術的な内容を分かりやすく伝えるために、技術部門のメンバーが監修する体制が効果的に機能しています。
この取り組みにより、BtoB企業でありながら一般消費者からの認知度も向上し、新卒応募者の「志望動機」にSNSでの情報発信を挙げる学生が増加したとのことです。また、社内でもSNSへの関心が高まり、コンテンツ提案が活発に行われるようになったそうです。

BtoB企業の採用SNS運用体制構築ステップ
ここまで見てきた成功事例や社内体制のポイントを踏まえ、BtoB企業が採用SNS運用体制を構築するための具体的なステップを解説します。
ステップ1:目的と目標の明確化
まず、採用SNS運用の目的と具体的な目標を明確にしましょう。「若手エンジニアの応募数を増やしたい」「自社の認知度を向上させたい」など、具体的なゴールを設定することが重要です。
目標設定のポイントは、SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)に基づくことです。例えば、「1年以内に技術職の20代応募者を30%増加させる」といった具体的な数値目標を設定しましょう。
目的と目標が明確になれば、それに合わせた運用体制の設計がしやすくなります。また、経営陣への説明材料としても活用できます。
ステップ2:適切なSNSプラットフォームの選定
BtoB企業の採用活動に適したSNSプラットフォームを選定します。各プラットフォームの特性と自社のターゲット層を照らし合わせて検討しましょう。
- Instagram:ビジュアル重視のプラットフォーム。職場環境や社員の様子を視覚的に伝えるのに適しています。20〜30代へのリーチに効果的です。
- X(旧Twitter):情報拡散力に優れたプラットフォーム。企業の最新情報や業界動向の発信に適しています。30〜40代のミドル層にもリーチできます。
- LinkedIn:ビジネス特化型SNS。特に専門職や経験者採用に効果的です。海外展開している企業や外国人材の採用を視野に入れている場合にも有用です。
- TikTok:若年層へのリーチに特化したプラットフォーム。短尺動画で企業の魅力を伝えることができます。Z世代の採用に力を入れたい企業に適しています。
- YouTube:詳細な情報発信が可能なプラットフォーム。企業紹介や職種説明、社員インタビューなど、じっくり見てもらいたいコンテンツに適しています。
すべてのプラットフォームで運用するのは負担が大きいため、まずは1〜2つに絞って始めることをおすすめします。ターゲットとする人材層が最も活発に利用しているプラットフォームを選びましょう。
ステップ3:運用チームの編成と役割分担
効果的なSNS運用のためには、適切なチーム編成と役割分担が重要です。以下のような役割を設定し、担当者を決めましょう。
- SNS運用責任者:全体戦略の立案と進捗管理を担当
- コンテンツ企画担当:投稿内容の企画立案を担当
- コンテンツ制作担当:写真・動画の撮影、編集を担当
- コミュニティ管理担当:コメント対応やメッセージ管理を担当
- 分析・レポート担当:データ分析と効果測定を担当
小規模な企業では、一人が複数の役割を兼任することもあるでしょう。その場合は、特に負担の大きいコンテンツ制作部分を外部に委託するという選択肢もあります。
また、先述した「SNSアンバサダー制度」のように、各部署から協力者を募り、情報収集やコンテンツ提案のネットワークを構築することも効果的です。
ステップ4:コンテンツ戦略の策定
BtoB企業の採用SNSで効果を上げるためには、計画的なコンテンツ戦略が不可欠です。以下のようなコンテンツカテゴリーをバランスよく組み合わせましょう。
- 企業文化・価値観の発信:経営理念や社風を伝えるコンテンツ
- 社員紹介:実際に働く社員の声や日常を紹介するコンテンツ
- 職場環境紹介:オフィスや工場、設備などの紹介コンテンツ
- 仕事内容紹介:各職種の具体的な業務内容を紹介するコンテンツ
- 技術・製品紹介:自社の技術力や製品の魅力を伝えるコンテンツ
- イベント・社内行事:社内イベントや研修の様子を伝えるコンテンツ
- 採用情報:募集職種や選考プロセスを紹介するコンテンツ
これらのコンテンツを月間・週間の投稿カレンダーに落とし込み、計画的に運用することが重要です。例えば、「毎週月曜は社員紹介、水曜は技術紹介、金曜は社内イベント」といったリズムを作ることで、継続的な運用が容易になります。
コンテンツ制作の負担を軽減するためには、「テンプレート化」も有効です。例えば、「#うちの会社の〇〇さん」というフォーマットを決めておき、毎回同じ質問に答えてもらうだけで投稿が完成するようにしておくと、制作の手間が大幅に削減できます。
ステップ5:運用ルールとガイドラインの策定
SNS運用を円滑に進めるためには、明確なルールとガイドラインが必要です。以下のような項目を含めたガイドラインを作成しましょう。
- 投稿ポリシー:投稿可能な内容と禁止事項
- トーン&マナー:文体や表現のトーンに関するガイドライン
- 写真・動画撮影ルール:撮影許可や肖像権に関するルール
- 承認フロー:投稿前の確認・承認プロセス
- 危機管理プロトコル:炎上時や問題発生時の対応手順
- パスワード管理:アカウント情報の管理ルール
ガイドラインは一度作成したら終わりではなく、運用を通じて得られた知見を基に定期的に更新していくことが重要です。
特に承認フローは、迅速な投稿と内容の適切性のバランスを考慮して設計しましょう。承認者が多すぎると投稿のタイミングを逃してしまいますが、チェック体制が不十分だと問題のある投稿が公開されるリスクが高まります。
ステップ6:効果測定の仕組み構築
採用SNS運用の効果を継続的に測定・評価するための仕組みを構築しましょう。以下のような指標を設定し、定期的に測定することをおすすめします。
- SNS指標:フォロワー数、エンゲージメント率、リーチ数など
- 採用指標:SNS経由の応募数、選考通過率、内定承諾率など
- 認知度指標:自社認知度調査、業界内での評判など
- コスト効率指標:採用一人あたりのコスト、従来手法との比較など
これらの指標を月次・四半期・年次でレポート化し、経営陣や関係部署に共有することで、SNS運用の価値を可視化しましょう。
また、応募者アンケートに「当社を知ったきっかけ」「応募を決めた理由」などの項目を設け、SNSの影響を直接測定することも効果的です。
BtoB企業の採用SNS運用を成功させるための実践的ヒント
最後に、BtoB企業が採用SNS運用を成功させるための実践的なヒントをいくつか紹介します。
ショート動画を活用した効果的な情報発信
近年、InstagramのリールやTikTokなどのショート動画フォーマットが若年層を中心に人気を集めています。BtoB企業においても、ショート動画を活用した情報発信が効果的です。
ショート動画の特徴は、短時間で視聴者の注目を引き、情報を簡潔に伝えられる点にあります。特に若手人材へのアプローチにおいて、長尺の企業紹介動画よりも効果的なケースが多いです。
ショート動画の制作には、以下のようなポイントを意識しましょう:
- 冒頭3秒で視聴者の注目を引く
- 一つの動画につき一つのメッセージに絞る
- テキストやキャプションを効果的に活用する
- BGMやエフェクトを適切に使用する
- 社員の自然な表情や動きを捉える
ある精密機器メーカーでは、「60秒でわかる〇〇の仕事」というシリーズのショート動画を制作し、各職種の業務内容を簡潔に紹介しています。このコンテンツは特に学生からの反響が高く、「具体的な仕事内容がイメージできた」という声が多数寄せられているそうです。
社員を巻き込んだ継続的な運用体制
SNS運用を長期的に継続するためには、担当者一人に負担が集中しない仕組みづくりが重要です。社員を巻き込んだ運用体制を構築することで、コンテンツの多様性確保と担当者の負担軽減を同時に実現できます。
社員巻き込みのポイントは以下の通りです:
- SNS運用の目的と意義を全社的に共有する
- 参加しやすい仕組み(投稿提案フォームなど)を用意する
- 貢献した社員を表彰・紹介する仕組みを作る
- 経営層自らが積極的に参加する姿勢を見せる
- 部署ごとの投稿担当月を設定するなど、公平な分担を行う
電子部品メーカーのC社では、社内イントラネットに「SNSネタ投稿箱」を設置し、誰でも気軽にネタ提供できる仕組みを構築。さらに、月間MVPとして優れた投稿アイデアを提供した社員を表彰する制度を導入したところ、社員からの投稿提案が大幅に増加したそうです。
外部リソースの効果的な活用
社内リソースだけでSNS運用を行うことが難しい場合は、外部リソースを効果的に活用することも検討しましょう。特に、コンテンツ制作や分析など、専門的なスキルが必要な部分は外部委託することで、質の高い運用が可能になります。
外部リソース活用の選択肢としては、以下のようなものがあります:
- SNS運用代行サービスの利用
- フリーランスのカメラマンやデザイナーとの協業
- 動画制作会社への制作委託
- SNSコンサルタントによる定期的なアドバイス
- 社員向けSNS研修の実施
月々20万円からの「ショート動画」中心の採用SNS運用支援サービスなど、BtoB企業向けに特化したサービスも登場しています。これらのサービスを活用することで、社内リソースを最小限に抑えながら、専門的なSNS運用のメリットを享受することができます。
特に初期段階では、外部の専門家のサポートを受けながら社内のノウハウを蓄積し、徐々に内製化していくアプローチも効果的です。
まとめ:BtoB企業の採用SNS運用成功の鍵
BtoB企業が採用SNSを効果的に運用するためには、適切な社内体制の構築が不可欠です。本記事で解説した5つの社内体制(経営陣の理解と関与、社内の協力体制とネタ共有文化、明文化されたSNSポリシー、担当者の適正と育成、効果測定とフィードバックサイクル)を整備することで、持続可能なSNS運用が実現します。
また、実際の運用においては、ショート動画の活用、社員の巻き込み、外部リソースの効果的な活用などの実践的なアプローチが成功の鍵となります。
BtoB企業の採用市場において、特に若手人材の獲得競争が激化する中、SNSを活用した採用マーケティングは、直接的な採用活動だけでなく、企業の認知度向上や企業イメージの構築にも寄与する重要な戦略です。
自社の特性や課題に合わせた運用体制を構築し、継続的な改善を重ねることで、採用SNSは強力な採用ツールとなるでしょう。
採用SNS運用に関するさらに詳しい情報や、BtoB企業向けの「ショート動画」中心の採用SNS運用支援サービスについては、下記のリンクから資料をダウンロードしてご確認ください。