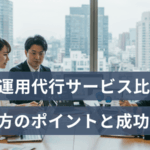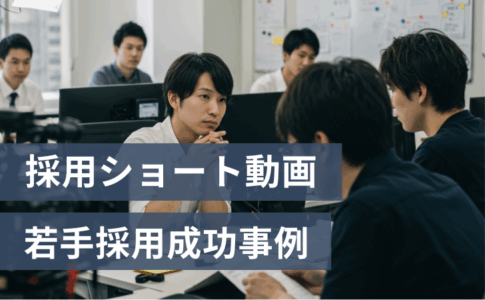採用ショート動画が注目される理由と市場動向
採用市場において、特に若手人材の獲得競争が激化する中、従来の採用手法だけでは効果が限定的になりつつあります。そんな状況を打破する新たな手法として、ショート動画を活用した採用戦略が急速に注目を集めています。
ショート動画とは、TikTokやInstagramリール、YouTubeショートなどで主流となっている1分以内の短尺動画コンテンツのこと。この短い時間で企業の魅力や社風、働く環境を効果的に伝えることができるのです。
なぜ今、採用活動にショート動画が必要なのでしょうか?
Z世代やミレニアル世代といったデジタルネイティブな若手人材は、長い企業説明よりも短くインパクトのある動画コンテンツを好む傾向があります。彼らの注目を集め、企業の魅力を伝えるには、彼らが日常的に触れているショート動画の形式が最適なのです。

2025年現在、採用市場においてショート動画の活用は急速に広がっています。特に東北地域では、人材不足が全国平均よりも1割以上深刻な状況にあり、企業の顔が見える動画コンテンツによって応募数を拡大する取り組みが活発化しています。
さらに、広告コストの高騰も企業の悩みの種。自社内でショート動画を制作・運用することで、中長期的な広告費用を抑制できるメリットも大きいのです。
採用ショート動画内製化のメリット
採用ショート動画を外注せず、社内で内製化することには数多くのメリットがあります。
まず最も大きなメリットは、コスト削減効果です。外部の制作会社に依頼すると1本あたり数十万円かかることもありますが、内製化すれば素材費と人件費のみで制作可能になります。月々20万円からの運用支援サービスを活用しても、専任担当者を雇用するよりもはるかにコスト効率が高いのです。
私が以前、中小企業の採用担当をしていたとき、動画制作会社に依頼したら見積もりが1本50万円でした。予算オーバーで断念せざるを得なかったのですが、今思えば内製化していれば何本も作れていたはず。そんな経験から、内製化の重要性を痛感しています。
次に、スピード感と柔軟性の向上が挙げられます。外部に依頼すると企画から納品まで数週間〜数ヶ月かかることも珍しくありませんが、内製化すれば企画から公開まで数日で完結することも可能です。
社内の雰囲気や出来事をタイムリーに発信できるのは、内製化ならではの強みといえるでしょう。

さらに、自社の魅力を最も理解しているのは外部の人間ではなく社員自身です。内製化によって社員が主体的に関わることで、より自社の魅力や文化を正確に伝えられるコンテンツが生まれます。
実際、採用SNSの運用を内製化した企業では、応募者の質が向上したという報告も多いのです。なぜなら、リアルな企業文化が伝わることでミスマッチが減少するからです。
また、内製化は社内のデジタルスキル向上にも貢献します。宮城県気仙沼市のサンリクテックが提供する「YouTubeショート内製化プログラム」では、台本作成に生成AI(ChatGPTやGemini等)を活用するなど、最新技術の社内導入も支援しています。
このように、動画制作のスキルだけでなく、デジタルマーケティングや最新テクノロジーの活用スキルも社内に蓄積できるのです。
内製化に必要な準備と基本ステップ
採用ショート動画の内製化を成功させるには、適切な準備と基本的な制作フローの確立が不可欠です。まずは必要な機材から見ていきましょう。
実は、高価な機材は必ずしも必要ありません。最新のスマートフォンであれば十分な画質で撮影可能です。それに加えて、小型三脚(1,000〜3,000円程度)、スマートフォン用のLEDライト(2,000〜5,000円程度)があれば基本的な撮影環境は整います。
音声品質を向上させたい場合は、ピンマイク(5,000〜10,000円程度)の追加も検討してみてください。これだけで、プロっぽい仕上がりになります。
私が初めて社内でショート動画を作ったとき、照明が足りずに暗い映像になってしまいました。安価なLEDライトを追加しただけで、見違えるように明るく視聴者を引き込む映像に変わったんです。小さな投資で大きな効果が得られることを実感しました。

次に、基本的な制作フローを確立しましょう。一般的なショート動画制作の流れは以下のようになります。
- 企画立案(伝えたいメッセージ、ターゲット、構成を決定)
- 台本・絵コンテ作成(30秒〜1分の尺に収まるよう簡潔に)
- 撮影準備(機材確認、出演者への説明)
- 撮影(複数テイク撮影することをおすすめ)
- 編集(スマートフォンアプリやPC用編集ソフトを使用)
- レビュー・修正
- 公開・分析
編集ツールについては、初心者でも扱いやすいものが多数あります。スマートフォンアプリでは「CapCut」「InShot」などが人気で、PCソフトでは「DaVinci Resolve」(無料版あり)がおすすめです。
特に「CapCut」はTikTokと同じ会社が開発しており、ショート動画に最適化された機能が豊富です。テンプレートも多数用意されているので、初めての方でも簡単に始められます。
また、内製化を成功させるためには、担当者の明確化も重要です。理想的には1〜2名の専任担当者を置くことですが、兼任でも構いません。サンリクテックの「YouTubeショート内製化プログラム」では、1名の社内担当者でも既存の業務フロー内で実装できるような仕組みとナレッジを3カ月で構築することを目指しています。
効果的な採用ショート動画の制作テクニック
採用ショート動画を制作する際、単に会社の紹介をするだけでは視聴者の心を掴むことはできません。効果的なコンテンツにするためのテクニックをご紹介します。
まず最も重要なのは、冒頭3秒で視聴者の注目を集めることです。TikTokやYouTubeショートでは、最初の数秒で視聴を続けるかどうかが決まります。
「当社は2005年設立の〜」といった一般的な企業紹介から始めるのではなく、「入社3年目で海外出張に行けました」「未経験から始めたプログラミングで大規模システムを構築」など、具体的で興味を引く内容から始めましょう。
あなたはスクロールを止めたくなるような冒頭を作れていますか?

次に、「人」にフォーカスすることが重要です。企業の設備や制度よりも、そこで働く人々の表情や声のほうが視聴者の共感を得やすいのです。
実際に働いている社員のリアルな声や、日常の一コマを見せることで、視聴者は「自分もここで働くイメージ」を持ちやすくなります。
先日、ある製造業の採用担当者から相談を受けました。「工場の設備を中心に撮影した動画が全く反応を得られない」とのこと。アドバイスに従って現場で働く若手社員を主役にした動画に変更したところ、応募が3倍に増えたそうです。人の存在が視聴者の感情を動かす力は計り知れません。
ショート動画の構成パターン
効果的なショート動画の構成パターンをいくつかご紹介します。
- 1日密着型:社員の1日に密着し、出社から退社までをダイジェストで見せる
- Q&A型:よくある質問に社員が答えていく
- ビフォーアフター型:入社前と入社後の変化を対比させる
- 職場ツアー型:オフィスや施設を案内する
- チャレンジ型:社内で流行している遊びやチャレンジを紹介
これらのパターンを組み合わせることで、バラエティに富んだコンテンツを継続的に発信できます。
また、トレンド音楽や人気のエフェクトを取り入れることも効果的です。ただし、企業イメージを損なわないよう注意が必要です。
編集面では、テンポの良さが重要です。カット割りを多くし、1カットあたり2〜3秒程度にすることで、視聴者を飽きさせない工夫をしましょう。
字幕も必須要素です。音声がオフでも内容が伝わるよう、要点を簡潔に字幕化します。ただし、文字が多すぎると読みにくくなるため、1画面あたり15文字程度に抑えるのがコツです。
内製化を成功させるための支援サービス活用法
採用ショート動画の内製化を進める際、すべてを自社だけで行うのは難しい場合もあります。そんなとき、外部の支援サービスを活用することで、スムーズに内製化を実現できます。
現在、採用ショート動画の内製化を支援するサービスが増えています。特に注目すべきは、月々20万円からの「ショート動画」中心の採用SNS運用支援サービスです。
このようなサービスは、BtoB企業を主なターゲットとしており、「認知度向上」「採用ブランディング」「リソース不足解消」「若手採用強化」「コスト削減」といった課題を抱える企業に最適なソリューションとなっています。
特に、採用SNSのノウハウがない企業や、今後中長期的に採用力を高めたいと考えている企業におすすめです。
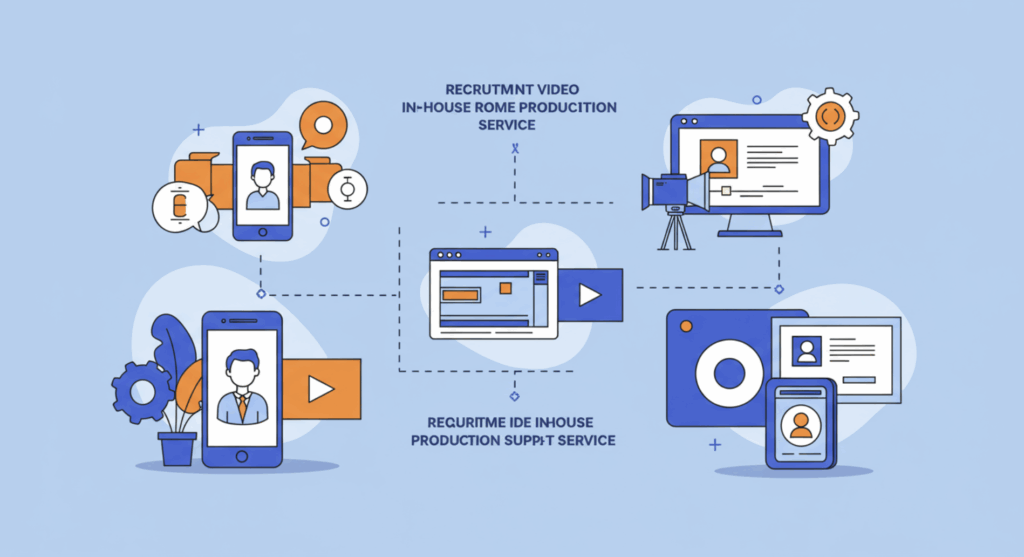
宮城県気仙沼市の合同会社サンリクテックが提供する「3カ月伴走型・YouTubeショート内製化プログラム」は、社内DX(マニュアル可視化・情報共有)と社外ブランディング/採用強化を、1分以内の縦型ショート動画を用いて自社内で実現できるように支援するプログラムです。
このプログラムでは、台本作成などにあたって生成AI(ChatGPTやGemini等)を使用するなど、最新技術の活用方法も学べます。1名の社内担当者でも、既存の業務フロー内で実装できる仕組みとノウハウを3カ月で構築することを目指しています。
また、株式会社美手紙が運営する「ショート動画屋さん」は、社会保険労務士事務所と連携した「ショート動画内製化支援プログラム」を提供しています。このサービスでは、企業内でのショート動画制作体制の構築から、ディレクション、広告出稿までを包括的に支援。助成金申請サポートも含まれているため、コスト面での負担も軽減できます。
どうですか?自社だけで悩むより、専門家のサポートを受けた方が効率的だと思いませんか?
これらのサービスを活用する際のポイントは、自社の課題やゴールを明確にしておくことです。「若手採用を強化したい」「社内のデジタルスキルを向上させたい」など、目的を明確にした上でサービスを選ぶことで、より効果的な支援を受けられます。
また、支援サービスを利用する期間中に、できるだけ多くのノウハウを社内に蓄積することが重要です。質問や相談を積極的に行い、専門家の知見を吸収しましょう。
成功事例から学ぶ効果的な採用ショート動画戦略
実際に採用ショート動画を内製化し、成功を収めている企業の事例から学ぶことは非常に価値があります。ここでは、いくつかの成功事例とそこから得られる教訓を紹介します。
ある製造業のBtoB企業では、工場で働く若手社員の1日を追ったショート動画シリーズを制作。特別なことは何もしていないにもかかわらず、リアルな職場の雰囲気と社員の等身大の姿が若年層に響き、応募者が前年比150%に増加しました。
この事例から学べるのは、「完璧な映像美よりも、リアルさが重要」ということ。高度な編集技術がなくても、等身大の社員の姿を見せることで十分に効果を発揮できるのです。
また、IT企業のある事例では、社員が自分の趣味や特技を披露する「#社員の素顔」シリーズを展開。仕事の様子だけでなく、プライベートの一面も見せることで、「この会社なら自分らしく働ける」というメッセージを伝えることに成功しました。
入社3年目のエンジニアが休日にバンド活動をしている様子を紹介した動画は、特に反響が大きく、「仕事と趣味を両立できる環境」という企業の強みを効果的にアピールできました。
「うちの会社には面白いコンテンツがない」と思っていませんか?

日常業務の中に、実は多くのコンテンツの種があるのです。
さらに、建設業界の企業では、「#建設現場のリアル」というハッシュタグで、現場で働く社員の声や、普段見ることのできない建設の裏側を紹介するショート動画を定期的に投稿。特に女性エンジニアが活躍する様子を積極的に発信したことで、女性応募者が増加したという事例もあります。
この事例からは、「ターゲットを明確にした発信が効果的」という教訓が得られます。採用したい人材像を明確にし、その層に響くコンテンツを意識的に制作することが重要です。
成功事例に共通するのは、「継続的な発信」という点です。1本や2本の動画ではなく、定期的に複数の動画を投稿することで、企業のファンを徐々に増やしていくことが成功の鍵となっています。
内製化によって制作コストを抑えられることで、この「継続性」が実現しやすくなるのです。
採用ショート動画の効果測定と改善サイクル
採用ショート動画を内製化して運用する際、効果測定と改善サイクルの確立は非常に重要です。どれだけ良い動画を作っても、その効果を測定し、継続的に改善していかなければ、最大の成果は得られません。
効果測定の基本的な指標としては、以下のようなものがあります。
- 視聴回数:動画が再生された総回数
- 視聴完了率:最後まで視聴された割合
- エンゲージメント率:いいね、コメント、シェアなどのアクション数
- フォロワー増加数:動画投稿によるアカウントフォロワーの増加
- 応募数・問い合わせ数:最終的な採用活動への影響
これらの指標を定期的に測定し、どのような内容・構成・投稿タイミングの動画が効果的だったかを分析します。
以前、ある製造業の採用担当者から「動画を投稿しても反応がイマイチ」という相談を受けました。分析してみると、平日の夜に投稿していたことが判明。ターゲットとする学生は週末の夜に最もSNSを利用する傾向があったため、投稿タイミングを変更したところ、エンゲージメントが3倍に増加したのです。
データに基づく小さな改善が大きな成果につながることを実感した瞬間でした。

効果測定の結果を踏まえた改善サイクルは、以下のようなステップで回していくことをおすすめします。
- 分析:データから成功・失敗要因を特定
- 仮説立案:改善のためのアイデアを複数考案
- テスト:異なるアプローチの動画を制作・投稿
- 効果測定:結果を数値で確認
- 改善:効果的だった要素を次回に活かす
このサイクルを回し続けることで、徐々に自社に最適な動画スタイルが見えてきます。
効果測定を行う際の重要なポイントは、「最終目的を見失わないこと」です。視聴回数やいいね数は重要な指標ですが、最終的には「採用」という目的にどれだけ貢献したかが最も重要です。
サンリクテックが提供する「YouTubeショート内製化プログラム」では、月1回の改善レポートと打ち合わせが含まれており、データに基づいた継続的な改善をサポートしています。
また、「ショート動画屋さん」のサービスでは、AIを活用した効果予測システムの開発も進められており、より精度の高いマーケティング戦略の立案が可能になる予定です。
効果測定と改善のサイクルを回し続けることで、初期の動画よりも格段に効果の高いコンテンツを制作できるようになります。
あなたの会社の採用動画は、毎回進化していますか?
2025年の最新トレンドと今後の展望
採用ショート動画の世界は日々進化しています。2025年現在のトレンドと今後の展望について見ていきましょう。
まず、現在の最新トレンドとして注目すべきは「リアル感の重視」です。過度に演出された企業PRよりも、実際の職場環境や社員の等身大の姿を見せるコンテンツが高い評価を得ています。
特に「1日密着型」の動画は、視聴者が自分自身をその環境に置き換えやすく、応募意欲を高める効果があります。
また、「インタラクティブ要素の導入」も進んでいます。視聴者参加型のQ&Aや、「この職種に興味がある方はいいねを押してください」といった簡単なインタラクションを促す仕掛けが効果を発揮しています。
そして、「社員が主役のユーザー生成コンテンツ(UGC)スタイル」も人気です。プロが作ったような完璧な映像よりも、社員自身が撮影・出演する素朴な動画の方が信頼性と共感を得やすいのです。

今後の展望としては、AIの活用がさらに進むでしょう。台本作成や簡単な編集作業はAIが支援し、人間はより創造的な部分に集中するというワークフローが一般的になると予想されます。
実際、サンリクテックの「YouTubeショート内製化プログラム」では、台本作成に生成AI(ChatGPTやGemini等)を活用するなど、最新技術の業務への導入も支援しています。
また、TikTok shopの日本進出を見据えたプランも登場しており、採用活動とEコマースの融合も今後のトレンドになる可能性があります。
さらに、メタバースやAR(拡張現実)を活用した没入型の採用体験も徐々に広がりつつあります。職場環境をバーチャルで体験できるコンテンツは、特に遠方の求職者へのアプローチに効果的です。
「うちの会社には最先端の技術を導入する余裕がない」
そう思われるかもしれませんが、実はこれらの技術は急速に一般化しており、導入ハードルは下がり続けています。月々20万円からの採用SNS運用支援サービスを活用すれば、最新トレンドを取り入れた採用戦略を展開することも十分可能なのです。
重要なのは、技術そのものではなく、自社の魅力を最適な形で伝えるという本質です。トレンドは手段であって目的ではありません。自社の強みや文化に合ったアプローチを選択することが成功の鍵となります。
まとめ:採用ショート動画内製化で実現する採用力強化
採用ショート動画の内製化は、単なるコスト削減策ではなく、企業の採用力を根本から強化する戦略的な取り組みです。本記事で解説してきた内容を振り返りましょう。
まず、採用市場では若手人材獲得のための競争が激化しており、従来の採用手法だけでは効果が限定的になっています。特に東北地域では人材不足が深刻化しており、「顔が見える」動画コンテンツによる差別化が重要です。
採用ショート動画の内製化には、コスト削減、スピード感と柔軟性の向上、自社の魅力を正確に伝える、社内のデジタルスキル向上など、多くのメリットがあります。
内製化に必要な準備としては、基本的な撮影機材(スマートフォン、三脚、LEDライトなど)の準備と、制作フローの確立が重要です。高価な機材は必ずしも必要なく、既存のリソースでも十分に始められます。
効果的な採用ショート動画を制作するためには、冒頭3秒での注目獲得、「人」にフォーカスした内容、テンポの良い編集、適切な字幕の活用などがポイントです。
内製化を支援するサービスとしては、月々20万円からの「ショート動画」中心の採用SNS運用支援や、サンリクテックの「3カ月伴走型・YouTubeショート内製化プログラム」、「ショート動画屋さん」の内製化支援プログラムなどがあります。
成功事例からは、リアルさの重要性、ターゲットを明確にした発信、継続的な投稿の価値などが学べます。また、効果測定と改善サイクルを確立することで、より効果的なコンテンツ制作が可能になります。
2025年の最新トレンドとしては、リアル感の重視、インタラクティブ要素の導入、UGCスタイルの活用などが挙げられ、今後はAI活用やAR技術の導入がさらに進むと予想されます。
採用ショート動画の内製化は、単に「動画を作る」という表面的な活動ではなく、企業の魅力を効果的に伝え、採用ブランディングを強化する戦略的な取り組みです。
今こそ、あなたの会社も採用ショート動画の内製化に取り組み、採用力を強化する時ではないでしょうか。
まずは小さく始めて、徐々に拡大していくアプローチがおすすめです。初期費用20万円が先着5社まで無料となるモニタープランも提供されていますので、この機会にぜひ検討してみてください。