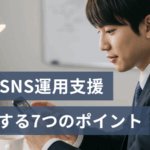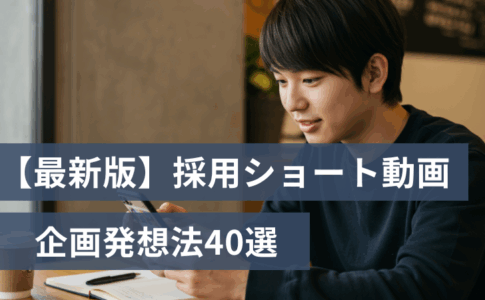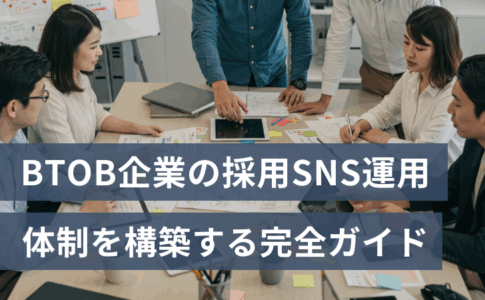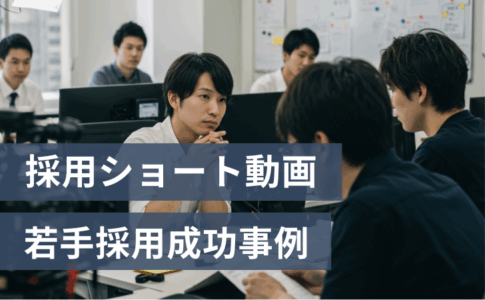採用ショート動画とは?2025年の採用市場における重要性
採用ショート動画とは、企業の魅力や社風、働く環境を短時間で伝える縦型の動画コンテンツです。TikTokやInstagramリール、YouTubeショートなどのプラットフォームで公開され、若年層を中心とした求職者にリーチする強力なツールとなっています。
2025年の採用市場では、Z世代(12〜28歳)の採用がますます重要になっています。彼らはデジタルネイティブ世代として、従来の採用手法よりもSNSを通じた情報収集を好む傾向にあります。
少子高齢化が進む日本において、若手人材の獲得競争は年々激化しています。企業は戦略的に次世代を担う人材を確保するため、Z世代の価値観やメディア接触習慣に合わせた採用手法を取り入れる必要があるのです。

ショート動画の最大の特徴は「短尺」であることです。15秒から30秒程度の内容が主流で、長くても2分程度に収まります。Google社とMondelez社の調査によると、最も平均視聴完了率が高いのは「30秒広告」とされています。
この長さは、視聴者の関心を維持するのに適した簡潔さがありながらも、記憶に残る印象を与えるために最適だと考えられています。短い時間で企業の魅力を凝縮して伝えられる点が、採用活動において大きな武器となるのです。
なぜ今、採用ショート動画が注目されているのか?
採用ショート動画が注目を集める理由は、Z世代の就職活動の変化にあります。彼らは幼少期からインターネットやスマートフォンに親しみ、独自の価値観やライフスタイルを持つデジタルネイティブ世代です。
従来の採用方法では心に響かないケースが多いため、Z世代特有の趣向やニーズを理解した採用戦略が求められています。ショート動画はそんな彼らの情報収集スタイルにぴったりなのです。
Z世代が求職活動においてSNSで情報収集を行う傾向が強まっており、企業のSNS投稿が求職者に興味を持ってもらうきっかけになっています。実際、Z世代を対象にした調査では、転職活動で採用ショート動画を参考にする割合は86.6%と、約9割にも及ぶことがわかっています。
さらに重要なのは、採用ショート動画の視聴後における志望度の変化です。調査結果によると、動画視聴後に志望度が上がった人の割合は77%に達し、志望度が下がった人はわずか1.5%しかいません。つまり、採用動画を視聴してもらうことは志望度アップに大きく貢献するのです。
あなたの企業は、この強力なツールを活用できていますか?

採用ショート動画のメリットは、拡散性の高さにもあります。SNS各社がショート動画に注力しているため、アルゴリズム上で拡散されやすい仕組みになっています。そのため、企業の認知度が向上し、顧客層が広がるのです。
また、動画という形式は文字に比べて多くの情報量があるため、短時間で企業の価値を効果的に伝えることができます。フォローされていないユーザーにも表示されるため、新規客取り込みにも有効で、ゼロからの立ち上げにも適しています。
さらに、動画によるコンテンツマーケティングは、従来の「モノ売り」から脱却し、「価値を伝える企業」としてのポジショニングを確立できます。コンテンツ量と比例して費用対効果も高くなっていくのです。
2025年トレンド!効果的な採用ショート動画の種類と特徴
2025年現在、採用ショート動画には様々な種類があります。それぞれの特徴を理解し、自社の採用戦略に合わせて最適なタイプを選びましょう。
まず押さえておきたいのが、「社員の1日に密着した動画」です。実際の業務風景や職場の雰囲気を伝えることで、入社後のミスマッチを防ぐ効果があります。朝の出社から夕方の退社までの流れを30秒程度にまとめることで、求職者は自分がその環境で働くイメージを具体的に持つことができます。
社員インタビュー・座談会動画
社員インタビューや座談会形式の動画は、実際に働いている社員の生の声を届けられる点が魅力です。特に若手社員の率直な意見は、同世代の求職者に強く響きます。
この形式では、「入社の決め手は何だったか」「仕事のやりがい」「成長できたと感じる瞬間」などのテーマで質問すると効果的です。社員の表情や話し方からも企業文化が伝わるため、テキストだけでは伝えきれない情報を提供できます。
ただし、台本通りの硬い受け答えは逆効果です。自然な会話の中から本音が垣間見える瞬間を捉えることが重要です。

企業文化・オフィス紹介動画
オフィス環境や企業文化を紹介する動画も人気です。オフィスのデザインや設備、休憩スペース、社員の交流風景などを映すことで、働く環境の魅力を視覚的に伝えられます。
特にZ世代はワークライフバランスを重視する傾向があるため、フレックスタイム制度やリモートワーク環境、副業ができる柔軟な働き方などをアピールすると効果的です。
LINEヤフーやレバレジーズなどの企業は、オフィス紹介動画で社内の雰囲気や福利厚生を効果的に伝え、応募者の関心を高めることに成功しています。
ショートドラマ形式
2025年のトレンドとして最も注目されているのが「ショートドラマ形式」の採用動画です。ストーリー性のある短い物語を通じて、企業の理念や価値観を伝える手法です。
例えば、新入社員が成長していく様子や、チームで困難を乗り越えるエピソードなどを演出することで、感情に訴えかける効果があります。視聴者は物語に没入することで、その企業で働くイメージをより鮮明に描けるようになります。
ショートドラマは、単なる情報提供を超えた「疑似体験」を提供できる点が強みです。視聴者は登場人物に感情移入することで、自分がその企業で働く姿を想像しやすくなります。これが購買行動(この場合は応募行動)につながるのです。
採用ショート動画制作の基本ステップ
効果的な採用ショート動画を制作するためには、計画的なアプローチが必要です。ここでは、制作の基本ステップを解説します。
まず最初に行うべきは、ターゲットとなる人材像の明確化です。どのような人材を採用したいのか、その人材はどのような価値観や興味を持っているのかを具体的に定義しましょう。
次に、伝えたいメッセージを明確にします。「なぜうちの会社で働くべきなのか」という問いに対する答えを、簡潔かつ魅力的に表現できるよう練り上げましょう。
企画・構成のポイント
採用ショート動画の企画段階では、以下の点に注意しましょう。
- 冒頭3秒で視聴者の注目を集める強烈なフックを用意する
- 1つの動画につき1つのメッセージに絞る
- ストーリーボードを作成し、各シーンの流れを事前に計画する
- 視聴者が求める情報(業務内容、社風、成長機会など)を盛り込む
- 最後に明確なCTA(応募ページへの誘導など)を入れる
特に重要なのは冒頭部分です。SNSでは最初の数秒で視聴継続が決まるため、インパクトのある映像や音声で視聴者の関心を引きつけることが重要です。

撮影・編集のテクニック
撮影時には、以下のテクニックを活用しましょう。
- 縦型フォーマット(9:16)で撮影する
- 自然光を活用し、必要に応じて補助照明を使用する
- 三脚やジンバルを使用して安定した映像を撮る
- マイクを使用して明瞭な音声を収録する
- 複数のアングルから撮影し、編集の自由度を高める
編集においては、テンポの良さがカギとなります。1カットあたり2〜3秒程度の短いカットを組み合わせることで、視聴者の興味を持続させられます。また、トレンド感のあるBGMや効果音を使用することで、若年層の共感を得やすくなります。
TikTokやInstagramなどのプラットフォームには、便利な編集機能が備わっています。特殊効果やテキストオーバーレイ、トランジションなどを活用して、プロフェッショナルな仕上がりを目指しましょう。
どうですか?自社でも作れそうな気がしてきませんか?
効果的な音楽・テキストの活用法
ショート動画において、音楽の選択は非常に重要です。適切なBGMは視聴者の感情を動かし、記憶に残りやすくします。若年層に人気のトラックを使用することで、親近感を生み出せます。
テキストオーバーレイも効果的に活用しましょう。音声がオフの環境でも内容が伝わるよう、キーメッセージを簡潔なテキストで表示します。ただし、文字量は最小限に抑え、読みやすいフォントとコントラストを選ぶことが重要です。
また、字幕を入れることで、音声が聞こえない環境でも内容を理解してもらえます。特に通勤電車内などでスマートフォンを見ている求職者にリーチするためには必須の要素です。
SNSプラットフォーム別の最適化戦略
採用ショート動画の効果を最大化するには、各SNSプラットフォームの特性を理解し、それぞれに最適化した戦略が必要です。ここでは、主要なプラットフォーム別の特徴と活用のポイントを解説します。
2025年現在、採用ショート動画の投稿に適したプラットフォームは主に4つあります。TikTok、Instagram(リール)、YouTube(ショート)、X(旧Twitter)です。それぞれのプラットフォームには独自の特徴があり、ターゲット層や目的に応じて使い分けることが重要です。
TikTok活用のポイント
TikTokは、ショート動画の先駆け的存在です。他のSNSがTikTokを追いかけるように、ショート動画機能を実装してきました。
TikTokの最大の特徴は、編集に関する機能が豊富な点です。誰でも簡単にハイクオリティな動画を作成・投稿できるよう設計されています。トレンド音楽やエフェクトを活用することで、若年層の興味を引きやすくなります。
また、TikTokのアルゴリズムは、アカウントそのものの規模よりも動画1本ずつの内容で評価される傾向にあります。つまり、フォロワー数が少なくても、魅力的なコンテンツを投稿すれば大きな拡散が期待できるのです。
採用活動においては、若手社員が主役となったカジュアルな企業紹介や、業務の裏側を見せる「デイ・イン・ザ・ライフ」形式の動画が効果的です。Z世代が共感できる内容を積極的に投稿することで、企業イメージの向上と応募増加につながります。

Instagram(リール)の活用法
Instagramのリール機能は、ビジュアル重視のプラットフォームとして人気です。特に「世界観」を重視したコンテンツが多く、理想や憧れをビジュアル化している点が特徴です。
採用活動では、洗練されたビジュアルで企業のブランドイメージを高めることができます。オフィス環境や社員の活き活きとした姿、企業文化を象徴するシーンなどを美しく映し出すことで、「この会社で働きたい」という憧れを喚起できます。
Instagramらしい「理想・憧れ・共感」を引き寄せるような構成が、ヒットのポイントとなるでしょう。また、ハッシュタグを効果的に活用することで、特定の興味を持つユーザーにリーチしやすくなります。
YouTube(ショート)の特徴と活用術
YouTubeショートは、世界最大の動画プラットフォームの強みを活かした機能です。通常の長尺動画とショート動画を組み合わせた戦略が取れる点が特徴的です。
例えば、60秒以内のショート動画で興味を引き、詳細な企業紹介や職種説明は長尺動画に誘導するという方法が効果的です。検索エンジンとしての機能も強いため、適切なタイトルや説明文を設定することで、求職者からの発見可能性が高まります。
また、YouTubeは情報収集目的で利用されることが多いため、「業界知識」「職種の解説」「キャリアアドバイス」など、教育的な価値のあるコンテンツが響きやすい傾向があります。
X(旧Twitter)での効果的な展開
X(旧Twitter)は、即時性と拡散力に優れたプラットフォームです。縦型動画の投稿も可能になり、採用活動にも活用できます。
Xの特徴は、ユーザー同士の会話が生まれやすい点です。採用動画を投稿した際に、質問や感想に迅速に返信することで、求職者との関係構築が可能になります。また、企業の人間味や個性を示すチャンスにもなります。
採用情報だけでなく、業界のトレンドや専門的な知見を発信することで、フォロワーを増やし、潜在的な応募者との接点を作ることができます。定期的な投稿と対話を心がけることが成功の鍵です。
成功事例から学ぶ!効果的な採用ショート動画のコツ
実際に採用ショート動画で成果を上げている企業の事例から、効果的なアプローチを学びましょう。ここでは、様々な業界の成功事例とそのポイントを紹介します。
成功している採用ショート動画には、いくつかの共通点があります。それは「真正性(オーセンティシティ)」「ストーリー性」「感情への訴えかけ」「明確なメッセージ」などです。
BtoB企業の採用動画事例
BtoB企業は一般消費者向け企業に比べて知名度が低いことが多く、事業内容も理解されにくい傾向があります。そのため、採用ショート動画では「何をしている会社なのか」をわかりやすく伝えることが重要です。
例えば、コンサルティング会社のデロイト トーマツグループは、「きのうのじぶんを超えていく、じぶんへ」というコンセプトの採用ブランドムービーを公開しています。多様な社員個人にスポットライトを当て、入社後の成長した姿を見せる演出により、視聴者自身の成長をイメージさせる効果があります。
また、PwCコンサルティングは、コンサルタントの実際の業務や成長ストーリーを短い動画で紹介し、専門性の高い仕事の魅力を伝えることに成功しています。
BtoB企業の採用動画で効果を上げるコツは、「複雑な事業内容をシンプルに伝える」「社会的インパクトを示す」「チームワークや成長機会を強調する」の3点です。
製造業・技術職の魅力を伝える事例
製造業や技術職の採用では、「ものづくりの面白さ」や「技術力」を視覚的に伝えることが効果的です。
例えば、ソニー株式会社の技術職向け採用動画では、最先端の技術開発現場や、エンジニアが熱中して取り組む姿を映し出すことで、技術者としての誇りや成長機会をアピールしています。
また、JR東日本の技術職採用動画では、鉄道インフラを支える技術の重要性や、社会貢献度の高さを強調しています。「縁の下の力持ち」的な仕事の価値を、ドラマチックに表現することで、技術職の魅力を伝えることに成功しています。
製造業・技術職の採用動画では、「技術の社会的意義」「チームでの協働」「技術的チャレンジ」を示すことが、応募意欲の向上につながります。
若手採用に成功している動画の特徴
Z世代を中心とした若手採用に成功している動画には、いくつかの共通点があります。
まず、「リアルさ」を重視していることです。過度に美化された企業イメージではなく、実際の職場環境や社員の等身大の姿を見せることで、信頼感を醸成しています。
次に、「ユーモア」や「トレンド感」を取り入れている点です。堅苦しくない企業文化を示すことで、若年層の共感を得ています。例えば、流行の音楽やエフェクトを活用した編集スタイルは、若年層の心を掴むのに効果的です。
さらに、「成長機会」や「社会的意義」を明確に示している点も特徴です。Z世代は自己成長や社会貢献に高い関心を持つため、これらの要素を強調することで応募意欲を高めることができます。
若手採用に成功している企業は、採用動画だけでなく、SNS全体の運用戦略が一貫しています。定期的な投稿や、コメントへの丁寧な返信など、継続的なコミュニケーションを心がけている点も見逃せません。
自社制作と外部委託の比較:どちらが適切?
採用ショート動画の制作方法には、自社で内製するか、専門業者に外部委託するかの2つの選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況に合った方法を選びましょう。
自社制作のメリットとデメリット
自社制作の最大のメリットは、コスト面です。専門業者に依頼する場合と比べて、初期投資を抑えることができます。スマートフォンのカメラ性能は年々向上しており、基本的な機材さえあれば、一定レベルの動画制作が可能になっています。
また、社内の実情や文化を熟知しているため、企業の魅力を自然に表現できる点も強みです。さらに、制作ノウハウが社内に蓄積されるため、継続的な発信が可能になります。
一方、デメリットとしては、プロフェッショナルな品質を実現するのが難しい点が挙げられます。照明や音声、編集技術などの専門知識がないと、アマチュア感が出てしまう恐れがあります。
また、社内リソースの確保も課題です。担当者の本業に加えて動画制作の負担がかかるため、継続的な運用が難しくなる可能性があります。
外部委託のメリットとデメリット
外部委託の最大のメリットは、プロフェッショナルな品質が保証される点です。専門業者は最新の機材や技術、トレンドに精通しているため、高品質な動画を制作できます。
また、企画から撮影、編集までをワンストップで依頼できるため、社内の負担を大幅に軽減できます。特に、採用SNSのノウハウがない企業や、リソース不足に悩む企業にとっては大きなメリットとなります。
デメリットとしては、コストがかかる点が挙げられます。ただし、2025年現在では月々20万円からの採用SNS運用支援サービスも登場しており、以前に比べて導入のハードルは下がっています。
また、外部業者が企業文化を十分に理解していないと、表面的な表現になってしまう恐れもあります。この点は、事前の綿密なコミュニケーションで解決できる課題です。
コスト比較と投資対効果
採用ショート動画の制作・運用にかかるコストは、選択する方法によって大きく異なります。
自社制作の場合、初期投資として基本的な撮影機材(スマートフォン用三脚、マイク、照明など)に5〜10万円程度、編集ソフトのサブスクリプションに月額1〜2万円程度が必要です。さらに、担当者の人件費(時間コスト)も考慮する必要があります。
外部委託の場合、2025年現在の市場相場では、1本あたり2万円〜のショート動画制作サービスや、月額20万円〜の運用支援サービスが提供されています。初期費用として20万円程度かかるケースが多いですが、先着5社まで無料になるようなモニタープランを提供している業者もあります。
投資対効果を考える際は、単に制作コストだけでなく、採用コスト全体の削減効果も考慮すべきです。効果的な採用ショート動画によって応募数が増加し、採用媒体費や採用期間の短縮につながれば、トータルでのコスト削減が期待できます。
また、採用だけでなく企業ブランディングにも寄与するため、中長期的な企業価値向上という観点からも投資効果を評価することが重要です。
採用ショート動画成功のための実践的アドバイス
最後に、採用ショート動画を成功させるための実践的なアドバイスをご紹介します。これらのポイントを押さえることで、効果的な採用動画の制作・運用が可能になります。
継続的な運用のコツ
採用ショート動画は1本だけでなく、継続的に発信することで効果が高まります。しかし、多忙な業務の中で定期的な更新を維持するのは容易ではありません。
継続的な運用のコツは、まず「コンテンツカレンダー」を作成することです。年間・四半期・月間の投稿計画を立て、テーマや担当者を事前に決めておくことで、計画的な制作が可能になります。
また、1日の撮影で複数の動画素材を撮りためておく「バッチ撮影」も効率的です。例えば、社員インタビューを行う際に、複数のテーマについて一度に撮影し、それを順次編集・投稿することで、制作の負担を分散できます。
さらに、ユーザー生成コンテンツ(UGC)の活用も検討しましょう。社員自身が日常業務や職場の雰囲気を撮影した動画を募集し、適切な編集を加えて投稿することで、多様な視点からの企業紹介が可能になります。
効果測定と改善サイクル
採用ショート動画の効果を最大化するには、定期的な効果測定と改善が欠かせません。
主要な測定指標としては、「視聴回数」「エンゲージメント率(いいね、コメント、シェアの数)」「視聴維持率(どこまで動画を見てもらえたか)」「コンバージョン(応募ページへの遷移数や実際の応募数)」などがあります。
これらの指標を定期的に分析し、どのような内容・表現が効果的だったかを把握することで、次回の制作に活かせます。例えば、冒頭部分での離脱が多い場合は、より強力なフックを用意する、コメントが多く集まる内容は関連テーマで展開するなど、データに基づいた改善が可能です。
PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回すことで、徐々に自社に最適な採用動画のスタイルが確立されていきます。
社内体制の整備と人材育成
採用ショート動画の取り組みを成功させるには、適切な社内体制の整備も重要です。
理想的には、採用担当者とマーケティング担当者が協力するチーム体制を構築することです。採用担当者は求める人材像や採用メッセージを明確にし、マーケティング担当者はそれを魅力的に表現する役割を担います。
また、基本的な動画制作スキルを持つ人材の育成も検討しましょう。外部研修やオンラインコースを活用して、撮影・編集の基礎知識を習得することで、内製化の可能性が広がります。
さらに、経営層の理解と支援を得ることも成功の鍵です。採用ショート動画の重要性や期待される効果を明確に説明し、必要なリソース(予算・時間・人員)の確保につなげましょう。
採用ショート動画は、単なるトレンドではなく、これからの採用活動に欠かせない戦略的ツールです。本記事で紹介した知識とノウハウを活かし、自社の採用力強化に取り組んでみてください。
より詳しい情報や、プロフェッショナルによる採用SNS運用支援サービスについては、ぜひ資料をご覧ください。