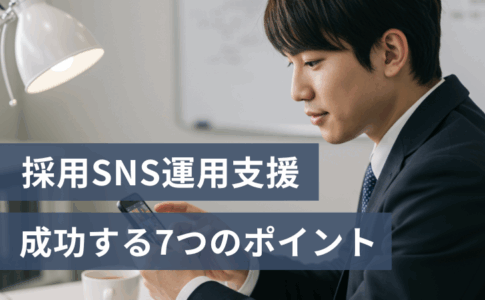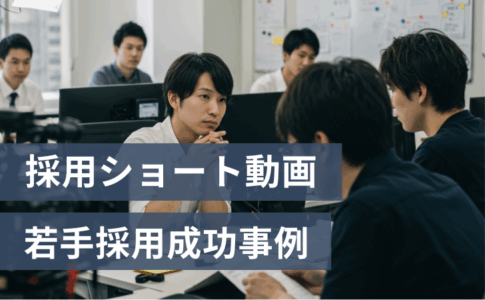採用SNS運用代行とは?若手採用を成功させる新たな戦略
「若手人材の採用がうまくいかない」
多くの企業が抱えるこの悩みに、新たな解決策として注目されているのが「採用SNS運用代行」です。特に2025年現在、ショート動画を中心としたSNS戦略が若手採用市場で大きな成果を上げています。従来の採用手法だけでは、デジタルネイティブ世代の心をつかむことが難しくなっているのです。
採用SNS運用代行とは、企業の採用活動におけるSNS運用を専門家チームが代行するサービスのこと。特にショート動画を活用した採用ブランディングは、Z世代やミレニアル世代へのアプローチに効果を発揮しています。
なぜ今、採用SNS運用代行が注目されているのでしょうか?
なぜ今、採用SNSとショート動画が重要なのか
採用市場が「売り手市場」の状態が続く中、企業間の人材獲得競争は年々激化しています。特に若年層の採用においては、従来の採用手法だけでは効果が限定的になりつつあるのが現状です。
Z世代の就職活動では、SNSを活用して情報を集める学生が急増しています。実際、25卒の学生を対象とした調査によると、約59.6%の学生が就職活動を進める上でSNSを活用して情報を集めていることがわかりました。
一方で、新卒採用にSNSを活用している企業は3割弱にとどまっています。この差が、採用におけるチャンスとなっているのです。

特に注目すべきは「ショート動画」の台頭です。
LINEリサーチによるWEB調査では、ショート動画を「ほぼ毎日見ている」人の割合は、10代で7割超、20代で約6割と若い年代ほど高くなっています。また、株式会社moovyの調査によれば、Z世代の77%が「採用動画の視聴後にその企業への志望度が上がった」と回答しているのです。
つまり、若手採用でSNSとショート動画を活用しないのは、大きな機会損失と言えるでしょう。
採用SNS運用代行サービスの特徴とメリット
「採用SNSの重要性はわかるけど、自社でやるのは難しい…」
多くの企業がこのような悩みを抱えています。そこで注目されているのが、月々20万円からの「ショート動画」中心の採用SNS運用支援サービスです。このサービスは、BtoB企業を主なターゲットとしており、「認知度向上」「採用ブランディング」「リソース不足解消」「若手採用強化」「コスト削減」といった課題を抱える企業に最適なソリューションとなっています。
採用SNS運用代行の主なメリット
- 専門知識不要:SNS運用のノウハウがなくても、専門家チームが代行
- リソース節約:社内リソースを最小限に抑えながら効果的な運用が可能
- コスト効率:専任担当者を雇用するよりも低コストで実現
- 若手層へのリーチ:ショート動画を通じてZ世代・ミレニアル世代に効果的にアプローチ
- 中長期的な採用力強化:継続的な情報発信による採用ブランディング構築
特に注目すべきは「ショート動画」を中心としたアプローチです。
TikTokやInstagramリール、YouTubeショートなどの短尺動画プラットフォームの人気が高まる中、若年層へのリーチを効果的に行うための戦略的選択となっています。従来の長尺の企業紹介動画やテキストベースの情報発信と比較して、視聴者の注目を集めやすく、拡散性も高いという特徴があるのです。

月額20万円からという料金設定は、専任の担当者を雇用するよりもコスト効率が高く、中小企業や採用予算に制約のある企業にとっても導入しやすい価格帯となっています。
あなたの会社も、採用SNS運用代行を活用して採用力を高めてみませんか?
2025年最新!採用SNS運用代行の成功事例5選
採用SNS運用代行サービスを導入して成功した企業の事例を見ていきましょう。特に2025年に入ってからは、ショート動画を中心とした戦略で大きな成果を上げている企業が増えています。
事例1:製造業B社(認知度向上と若手採用強化)
BtoB製造業のB社は、知名度の低さから若手採用に苦戦していました。採用SNS運用代行サービスを導入し、TikTokとInstagramでショート動画による情報発信を開始。工場内の最新設備や、若手社員が活躍する様子を15〜30秒の動画で紹介しました。
特に効果があったのは、「#製造業の裏側」というハッシュタグを使った工場内の意外な光景を紹介する動画シリーズ。視聴者からの「こんな最新設備があるなんて知らなかった」「思っていたより清潔でカッコいい」といったコメントが多数寄せられました。
結果として、SNS運用開始から3ヶ月で応募者数が前年比180%に増加。特に20代前半の応募が大幅に増え、採用コストも1人あたり約25%削減できました。
事例2:IT企業C社(企業文化と働き方の可視化)
システム開発を手がけるC社は、優秀なエンジニアの獲得に苦戦していました。採用SNS運用代行を導入し、YouTubeショートとInstagramリールで「1日密着」シリーズを展開。様々な職種のスタッフに密着し、実際の業務内容や社内の雰囲気を30秒程度の動画で紹介しました。

特に反響が大きかったのは、リモートワークとオフィスワークを組み合わせた柔軟な働き方や、社内イベントの様子を紹介する動画でした。「自分もこんな環境で働きたい」というコメントが多数寄せられ、エンゲージメント率は平均15%を記録。
結果として、SNS経由の応募者が半年で3倍に増加。特筆すべきは応募者の質の向上で、面接通過率が前年比で25%アップしました。
事例3:建設会社D社(若手社員の活躍をリアルに発信)
建設業界のD社は、若年層の「建設業=きつい、危険」というイメージを払拭するため、TikTokを中心にショート動画の発信を開始。最新のICT建機を操作する若手社員や、ドローンを活用した測量の様子など、最新技術を駆使する建設現場の魅力を発信しました。
20代の若手社員が主役となり、現場の面白エピソードや、やりがいを語る動画が特に人気を集めました。「建設業ってこんなにハイテクなんだ」「若いうちから大きなプロジェクトに関われるのは魅力的」といった反応が多数。
結果、TikTokのフォロワーは半年で5,000人を突破し、新卒応募者は前年比150%増。特に工業高校や理系大学からの応募が増加しました。
事例4:人材紹介会社E社(転職のリスクを払拭する戦略)
人材紹介会社E社は、転職に対する不安や躊躇を解消するため、InstagramとTikTokでショート動画による情報発信を開始。「転職成功者の声」や「転職でよくある質問」などのコンテンツを30秒程度の動画にまとめました。
特に効果的だったのは、実際の転職成功者が登場し、転職前の不安と転職後の変化を語る「ビフォーアフター」シリーズ。リアルな体験談が視聴者の共感を呼び、コメント欄では質問や相談が活発に行われました。
結果として、SNS経由の問い合わせが3ヶ月で62件増加。1件あたりの獲得コストは3,513円と、従来の広告手法と比較して大幅に効率化されました。

事例5:軽貨物運送業F社(柔軟な働き方をアピール)
軽貨物運送業のF社は、ドライバー不足に悩んでいました。採用SNS運用代行サービスを導入し、TikTokとInstagramでショート動画による情報発信を開始。「1日の流れ」や「給与の仕組み」、「シフトの柔軟性」などをわかりやすく紹介しました。
特に反響が大きかったのは、実際のドライバーが登場し、仕事のやりがいや自由な働き方を紹介する動画。「自分のペースで働ける」「思ったより稼げる」といった現場の声が、視聴者の不安を解消する効果を発揮しました。
結果として、SNS経由の応募が42件増加。1件あたりの獲得コストは1,683円と非常に効率的な採用活動が実現しました。
ショート動画を活用した採用SNS戦略の成功ポイント
成功事例から見えてくる、ショート動画を活用した採用SNS戦略の成功ポイントをご紹介します。
1. リアルな企業文化の可視化
求職者が最も知りたいのは「入社後の実際の姿」です。ショート動画では、オフィスの雰囲気や社員の日常、チームの連携など、求人票やホームページでは伝わりにくいリアルな企業文化を可視化できます。
例えば、社員の1日に密着した動画や、ランチタイムの様子、チーム会議の一場面など、企業の日常を切り取った動画は高い共感を得られます。「この会社で働くイメージが湧く」と感じてもらえれば、応募へのハードルが下がるのです。
実際に成功している企業では、過度に演出された内容よりも、自然体で撮影された動画の方が視聴者からの反応が良い傾向にあります。
2. 社員を主役にした共感性の高いストーリー
数字やデータよりも、人の顔が見える「ストーリー」の方が記憶に残ります。特に若手社員を主役にした動画は、同世代の求職者の共感を得やすいでしょう。
入社の決め手、仕事のやりがい、成長できた瞬間など、個人の体験談をベースにしたショート動画は、視聴者の感情に訴えかける力があります。「自分もこんな経験がしたい」と思わせることが、応募につながるのです。

あなたの会社でも、若手社員の声を集めてみませんか?
3. プラットフォーム特性を活かした最適化
各SNSプラットフォームには、それぞれ特性があります。成功している企業は、プラットフォームごとの特徴を理解し、最適化された戦略を展開しています。
- TikTok:トレンドを取り入れた親しみやすいコンテンツが効果的。10代後半〜20代前半へのリーチに強み
- Instagram:ビジュアル重視のスタイリッシュな内容が好まれる。20代〜30代へのアプローチに効果的
- YouTube:やや長めの動画も可能。検索性が高く、情報を求めるユーザーへのアプローチに適している
同じ内容でも、プラットフォームに合わせて尺や表現方法を変えることで、効果が大きく変わります。各プラットフォームのアルゴリズムや視聴者の傾向を理解した上で、最適な戦略を立てることが重要です。
4. 一貫性のある継続的な発信
SNS運用で最も重要なのは「継続性」です。散発的な投稿では効果は限定的で、定期的かつ一貫性のある発信が信頼構築につながります。
成功している企業では、週に2〜3回の定期投稿を3ヶ月以上継続することで、フォロワー数や応募数の増加を実現しています。また、コンテンツのテーマやトーン&マナーに一貫性を持たせることで、企業ブランドの認知と理解を促進しています。
採用SNS運用代行サービスの最大のメリットは、この「継続的な発信」をプロに任せられる点にあります。社内リソースが限られていても、質の高い情報発信を続けられるのです。
採用SNS運用代行サービスの選び方
採用SNS運用代行サービスを導入する際、どのような点に注目して選べばよいのでしょうか。
1. 実績とポートフォリオの確認
まずは、そのサービスがこれまでに手がけた実績やポートフォリオを確認しましょう。特に自社と同じ業界や、似たような課題を持つ企業の事例があれば参考になります。
「応募数が何件増えた」「採用コストが何%削減できた」といった具体的な数字があれば、より信頼性が高いと言えるでしょう。また、実際の動画コンテンツを見て、クオリティや企業文化の表現力をチェックすることも大切です。
ただし、数字だけでなく、応募者の質や採用後の定着率などの質的な成果も確認できるとベストです。
2. サービス内容と料金体系の透明性
採用SNS運用代行サービスの内容は各社によって異なります。以下の点が明確になっているか確認しましょう。
- 月間の動画制作本数
- 運用するSNSプラットフォームの種類
- 撮影・編集の有無と頻度
- 戦略立案やコンサルティングの有無
- 効果測定とレポーティングの頻度と内容
- 追加料金が発生するケース
月々20万円からというのが一般的な相場ですが、サービス内容によって料金は変わります。重要なのは、料金に見合った価値があるかどうかです。
初期費用が無料になるキャンペーンなどもチェックしておくと良いでしょう。中には、初期費用20万円を先着5社まで無料にするようなモニタープランを提供している会社もあります。
3. コミュニケーション体制と柔軟性
採用SNS運用は、企業の「顔」となる重要な活動です。担当者との円滑なコミュニケーションが取れるかどうかは、成功の鍵を握ります。
定期的なミーティングの頻度や、フィードバックの反映プロセス、緊急時の対応体制などを事前に確認しておきましょう。また、自社の要望や状況の変化に柔軟に対応してくれるかどうかも重要なポイントです。
特に、撮影のためのスケジュール調整や、社内の承認プロセスへの理解など、実務面での柔軟性は日々の運用をスムーズにする上で欠かせません。
4. データ分析と改善提案の質
優れた採用SNS運用代行サービスは、単に動画を制作・投稿するだけでなく、データに基づいた分析と改善提案を行います。
視聴回数やエンゲージメント率といった基本的な指標だけでなく、どの動画がどのような層に響いたのか、応募行動につながったのはどのようなコンテンツだったのかなど、より深い分析ができるサービスを選びましょう。
また、分析結果をもとに次の施策を提案してくれる「PDCAサイクル」の回し方も重要です。データを活かした継続的な改善が、採用成果を最大化します。
採用SNS運用代行の導入ステップと成功のポイント
採用SNS運用代行サービスの導入を決めたら、どのようなステップで進めればよいのでしょうか。成功のポイントとともに解説します。
1. 明確な目標設定と戦略立案
まずは、採用SNSを通じて達成したい目標を明確にしましょう。「認知度向上」「応募数増加」「採用コスト削減」など、具体的な数値目標があるとベターです。
目標が定まったら、それに合わせた戦略を立案します。ターゲットとなる人材像、訴求したい自社の魅力、活用するSNSプラットフォーム、発信するコンテンツの方向性などを決定します。
この段階で運用代行サービスと密にコミュニケーションを取り、専門家の知見を活かした戦略づくりを行うことが重要です。
2. コンテンツプランニングと素材準備
戦略に基づいて、具体的なコンテンツプランを作成します。3〜6ヶ月程度の中期的な計画を立てることで、一貫性のある発信が可能になります。
社員インタビュー、オフィスツアー、業務紹介、社内イベントなど、どのようなコンテンツを、どのタイミングで発信するかを決めましょう。また、撮影に必要な場所や人員の調整、社内承認プロセスの確認なども事前に行っておくと安心です。
私が以前関わった製造業の事例では、工場の撮影許可を得るのに時間がかかり、スケジュールが大幅に遅れてしまったことがありました。事前の準備と社内調整は非常に重要です。
3. 撮影・制作と投稿運用
計画に基づいて、実際の撮影と動画制作を行います。ショート動画は15〜60秒程度の短い尺ですが、その分メッセージを凝縮し、インパクトのある内容にすることが重要です。
制作された動画は、各SNSプラットフォームの特性に合わせて最適化し、計画的に投稿します。投稿のタイミングや頻度、ハッシュタグの活用なども、効果を左右する重要な要素です。
この段階では、運用代行サービスのノウハウを最大限に活用しましょう。プラットフォームごとのアルゴリズムの特性や、投稿に最適な時間帯など、専門的な知識に基づいた運用が効果を高めます。
4. 効果測定と継続的な改善
定期的に効果測定を行い、PDCAサイクルを回していくことが成功の鍵です。視聴回数、エンゲージメント率、フォロワー数の増加といった指標だけでなく、実際の応募数や採用コストへの影響も分析しましょう。
効果測定の結果に基づいて、コンテンツの方向性や投稿戦略を適宜調整していきます。初期の想定通りに進まないこともありますが、データに基づいて柔軟に対応することで、徐々に効果を高めていくことができます。
採用SNS運用は、短期的な成果を求めるものではなく、中長期的な採用ブランディング構築のための投資と考えるべきでしょう。
2025年、採用SNS運用代行の最新トレンド
2025年現在、採用SNS運用代行サービスにはどのような最新トレンドがあるのでしょうか。市場の動向を見ていきましょう。
1. 「ショート動画」の主流化と専門性の高まり
2025年の採用SNS運用において最も顕著なトレンドは、「ショート動画」の主流化です。TikTok、Instagram、YouTube、LINEなど主要SNSが軒並みショート動画機能に注力している状況を反映し、採用コンテンツもショート動画中心にシフトしています。
特に注目すべきは、単なる「短い動画」ではなく、各プラットフォーム特有の文法や視聴者心理を理解した専門的なショート動画制作の需要が高まっている点です。トレンド音楽の活用や、最初の3秒で視聴者の注意を引く技術など、専門的なノウハウが重要になっています。
そのため、採用SNS運用代行サービスも、ショート動画に特化した専門チームを持つ会社が選ばれる傾向にあります。
2. データ駆動型の戦略立案と効果測定の高度化
2025年の採用SNS運用では、感覚や経験則だけでなく、データに基づいた戦略立案と効果測定が当たり前になっています。
視聴完了率、エンゲージメント率、コンバージョン率など、様々な指標を分析し、どのようなコンテンツがどのような層に響くのかを科学的に検証するアプローチが主流です。また、A/Bテストを活用して、異なるアプローチの効果を比較検証する手法も広く採用されています。
先進的な採用SNS運用代行サービスでは、独自の分析ツールやダッシュボードを提供し、クライアントがリアルタイムで効果を確認できる体制を整えています。
3. 採用と社内活性化の融合
採用SNSの運用が、単なる採用活動の枠を超え、社内活性化やエンプロイーエンゲージメント向上にも寄与するという認識が広がっています。
社員が主役となるショート動画の制作過程自体が、社内コミュニケーションの活性化や帰属意識の向上につながるケースも多く報告されています。また、社内で話題になった動画が社員のSNSでシェアされることで、オーガニックなリーチが拡大するという好循環も生まれています。
先進的な採用SNS運用代行サービスでは、この「採用×社内活性化」の相乗効果を最大化するプランを提案しています。
4. AI活用による効率化と個別最適化
2025年の採用SNS運用では、AI技術の活用が進んでいます。動画編集の効率化、パーソナライズされたコンテンツ推薦、投稿タイミングの最適化など、様々な場面でAIが活用されています。
特に注目されているのは、蓄積されたデータをAIが分析し、より効果的なコンテンツ戦略を提案する機能です。「この層にはこのようなメッセージが効果的」「この時間帯に投稿すると反応が良い」といった知見を、AIが自動的に抽出して提案します。
ただし、AIはあくまでツールであり、企業の魅力を真に伝えるためには、人間の感性や戦略的思考が不可欠です。最新の採用SNS運用代行サービスは、AIと人間の強みを組み合わせたハイブリッドアプローチを採用しています。
採用SNS運用代行サービス導入時によくある質問
最後に、採用SNS運用代行サービスの導入を検討する際によくある質問とその回答をご紹介します。
Q1: 自社でSNS運用するのと比べて、どのようなメリットがありますか?
採用SNS運用代行サービスの最大のメリットは、専門的なノウハウとリソースを外部から調達できる点です。特にショート動画の制作には、企画力、撮影技術、編集スキル、トレンド把握など、多岐にわたる専門知識が必要です。
また、継続的な運用には相応の工数が必要ですが、代行サービスを利用することで社内リソースを最小限に抑えながら、質の高い情報発信を続けることができます。さらに、複数のSNSプラットフォームの特性を理解し、最適な戦略を立案・実行するノウハウも得られます。
結果として、自社運用と比較して、より効果的かつ効率的な採用SNS活用が可能になります。
Q2: どのくらいの期間で効果が出始めますか?
採用SNS運用の効果は、一般的に3〜6ヶ月程度で表れ始めます。ただし、企業の知名度や業界、ターゲット層によって差があります。
初期段階では、フォロワー数やエンゲージメント率の向上など、SNS上の指標が改善します。その後、サイトへの流入や資料請求、応募といった具体的なアクションにつながっていきます。
採用SNS運用は中長期的な採用ブランディング構築の施策であり、即効性を求めるものではありません。しかし、継続的な運用によって、徐々に採用力が高まっていくことが期待できます。
Q3: 社内の協力はどの程度必要ですか?
採用SNS運用代行サービスは、企画から制作、投稿、分析までをプロに任せられるサービスですが、全く社内の協力が不要というわけではありません。
最低限必要なのは、企業の魅力や採用方針の共有、撮影協力者の調整、コンテンツの承認プロセスなどです。特に初期段階では、企業文化や訴求したいポイントを正確に伝えるために、ある程度の時間を確保する必要があります。
ただし、一度関係性が構築されれば、月に数時間程度の確認作業だけで運用が可能になるケースが多いです。社内リソースの状況に合わせて、関与の度合いを調整できるサービスを選ぶと良いでしょう。
Q4: 月額20万円の費用対効果はどうですか?
月額20万円の費用対効果は、採用にかかる総コストと比較して考えるとわかりやすいでしょう。
一般的に、採用1名あたりのコストは、求人広告や人材紹介会社の利用を含めると、数十万円から数百万円かかると言われています。採用SNS運用代行によって応募数が増加し、採用コストが削減できれば、十分な費用対効果が見込めます。
また、採用SNS運用は単なる採用活動だけでなく、企業ブランディングの強化や、社内の活性化、既存社員のエンゲージメント向上にも寄与します。これらの副次的効果も含めて考えると、月額20万円という投資は十分に合理的と言えるでしょう。
初期費用が無料になるモニタープランなどを活用すれば、さらにコストパフォーマンスは向上します。
まとめ:ショート動画で若手採用を成功させるために
2025年の採用市場において、SNSとショート動画を活用した戦略は、若手人材獲得の鍵となっています。特にZ世代やミレニアル世代へのアプローチには、彼らが日常的に利用するプラットフォームでの情報発信が効果的です。
採用SNS運用代行サービスは、専門的なノウハウとリソースを外部から調達することで、効果的かつ効率的な採用SNS活用を可能にします。月々20万円からという料金設定も、採用コスト全体から見れば十分に合理的な投資と言えるでしょう。
成功のポイントは、リアルな企業文化の可視化、社員を主役にした共感性の高いストーリー、プラットフォーム特性を活かした最適化、そして一貫性のある継続的な発信です。これらを実践することで、単なる採用活動の枠を超えた、企業ブランディングの強化や社内活性化にもつながります。
採用市場の競争が激化する中、従来の採用手法だけでは限界があります。ショート動画を中心とした採用SNS運用を取り入れ、若手人材に選ばれる企業を目指しましょう。
あなたの企業も、採用SNS運用代行サービスを活用して、採用力を高めてみませんか?