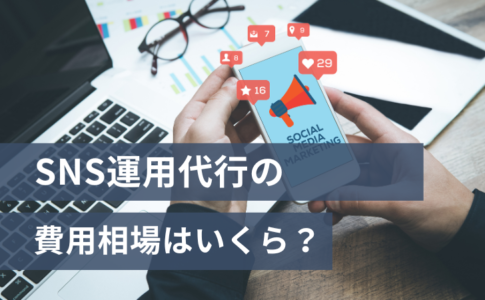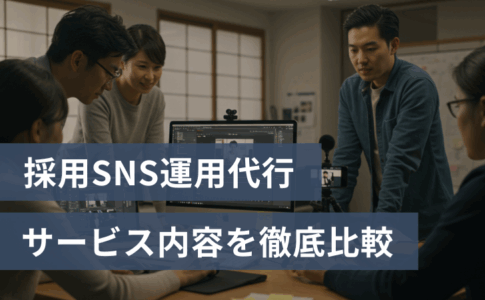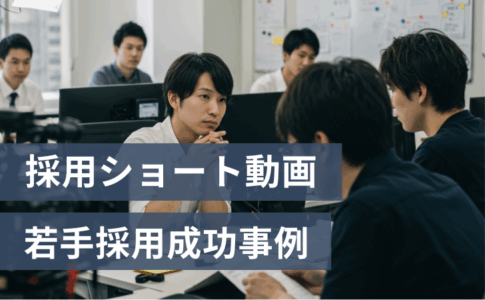ショート動画が採用市場を変える理由
「採用に力を入れているのに、なかなか若手人材が集まらない…」
多くの企業の採用担当者がこんな悩みを抱えています。特にBtoB企業では、自社の魅力を効果的に伝えることに苦戦しているケースが少なくありません。従来の採用手法だけでは、デジタルネイティブな若年層にリーチするのが難しくなっているのです。
そんな中で注目を集めているのが「ショート動画」を活用した採用ストーリーテリングです。TikTokやInstagramリール、YouTubeショートなどの短尺動画プラットフォームの台頭により、企業の採用コミュニケーション戦略にも大きな変化が起きています。

ショート動画は、わずか数分、時には数十秒という短い時間で視聴者の心を掴み、強いメッセージを届けることができます。特に若年層を中心に、短尺動画プラットフォームでの情報消費が一般化する中、採用市場でもその波が押し寄せているのです。
2025年現在、人材獲得競争が激化する中で、いかに自社の魅力を効果的に伝えるかが採用成功の鍵となっています。ショート動画を活用したストーリーテリングは、従来の採用手法では届かなかった層にも深くリーチできる可能性を秘めているのです。
なぜ今、採用にショート動画が効果的なのか
若手人材の獲得に苦戦している企業が多い理由の一つは、彼らの情報収集方法が大きく変化しているからです。
Z世代やミレニアル世代は、長い文章や静止画よりも、短くて印象的な動画コンテンツを好む傾向があります。彼らは1日に何十、何百もの短尺動画を消費し、その中から自分に関連性の高い情報を瞬時に選別しています。このような環境で育った世代に対して、従来の採用広告や企業説明会だけでアプローチするのは、もはや十分とは言えないのです。
ショート動画が採用に効果的な理由は主に以下の4つあります。
- 高い情報伝達効率:短時間で企業の雰囲気や価値観を伝えられる
- 感情に訴えかける力:ストーリーを通じて共感や興味を引き出せる
- 拡散性の高さ:SNSでシェアされやすく、リーチが広がる
- 若年層との親和性:Z世代やミレニアル世代の情報消費習慣に合致
特に注目すべきは、ショート動画の「ストーリーテリング」としての力です。単なる企業情報の羅列ではなく、感情に訴えかけるストーリーを通じて、視聴者の心に残るメッセージを届けることができます。

三井住友海上火災保険株式会社が2025年2月に開催したオンラインセミナー「今すぐ使える!ショート動画を活用した人材採用」では、若年層に人気のショート動画を活用した採用手法について詳しく解説されました。このセミナーでは、魅力的なコンテンツの作成方法やSNSの運用方法が紹介され、人材採用に課題を抱える企業から大きな注目を集めました。
このように、採用市場において「ショート動画×ストーリーテリング」という新たなアプローチが急速に広がっているのです。
成功するショート動画採用の3つの要素
ショート動画を採用に活用するといっても、ただ会社の様子を撮影して投稿すれば良いわけではありません。
実際に成果を上げている企業のショート動画には、共通する重要な要素があります。ここでは、採用ショート動画が成功するための3つの核心的要素を解説します。
1. 共感を生むストーリー設計
最も重要なのは、視聴者の共感を呼ぶストーリー設計です。企業の強みや特徴を単に列挙するのではなく、「なぜその仕事が意味を持つのか」「どんな人が活躍しているのか」といった物語性を持たせることが重要です。
例えば、社員の一日を追ったドキュメンタリー風の動画や、入社後のギャップを正直に語る動画などは、視聴者の興味を引きやすいでしょう。
あなたも思い出してみてください。数字やデータよりも、心に残るのは「物語」ではありませんか?
近年、企業PRにショートドラマを活用する事例が増えています。株式会社ワールドチェンジアナリシスのブログによれば、「広告より共感!ショートドラマを活用した新時代のマーケティング」として、ストーリー性を活かしたショートドラマが注目を集めています。企業がショートドラマを活用することで、押しつけがましくない自然な形でブランドメッセージを伝えることができるのです。
2. 視聴者を飽きさせない演出
ショート動画の最大の課題は、視聴者の注意を最後まで引きつけることです。アメリカのSNS「Snapchat」では、約70%のユーザーが最後まで広告を視聴せずに3秒でスキップしているというデータもあります。
この短い注意スパンに対応するためには、冒頭の3秒で興味を引く「フック」が必須です。また、テンポの良い編集や、意外性のある展開を取り入れることで、最後まで視聴してもらえる可能性が高まります。

動画制作・映像制作のCrevo VIDEO SQUAREによれば、ショートドラマは縦型フォーマットが特徴で、スマホでの視聴に最適化されており、片手で手軽に楽しめる点が魅力です。また、数分程度の短い尺で展開されるストーリーが中心となるため、スキマ時間を活用して視聴しやすいというメリットがあります。
採用動画においても、この「手軽さ」と「スキマ時間での視聴」を意識した演出が効果的です。
3. 拡散を促す仕掛け
良質なショート動画は、視聴者自身によって拡散される可能性を秘めています。そのためには、シェアしたくなる要素を意図的に盛り込むことが重要です。
例えば、「#クーリッシュでないとルーティン」というハッシュタグチャレンジを実施したロッテのショート動画は、YouTube Works Awards Japan 2025のファイナリストに選出されるほどの成功を収めました。このように、視聴者が参加したくなるような仕掛けを用意することで、自然な拡散が期待できます。
また、I-neのナイトケアビューティーブランド「YOLU」は、アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部とコラボレーションし、ライブ配信中にメンバーが寝落ちするという意外性のある企画を実施。この斬新な企画は大きな話題を呼び、2ヶ月で販売数100万個を突破する成果を上げました。
採用においても、このような「意外性」や「参加型の仕掛け」は、大きな拡散効果をもたらす可能性があります。
採用ショート動画の成功事例から学ぶ
理論だけでなく、実際の成功事例から学ぶことも重要です。ここでは、ショート動画を活用して採用成功に導いた企業の事例を紹介します。
飲食業界のショート動画求人サービス「グルメバイトちゃん」
株式会社シンクロ・フードが運営する「グルメバイトちゃん」は、飲食店のアルバイト募集をショート動画にして、SNSやWebメディアに掲載するサービスです。2025年3月には掲載店舗数が500を突破し、大きな注目を集めています。
このサービスの特徴は、従来の求人メディアでは伝えきれなかった「お店の雰囲気」や「働く楽しさ」をショート動画で表現している点です。お仕事体験動画を見た学生から「楽しそう。働いてみたい」という反応を得て、応募につながっています。
特に、おしゃれ自由度や飲食店の雰囲気など、既存の求人メディアでは訴求できない角度からアプローチできる点が、このサービスの強みとなっています。

日本航空(JAL)の「旅する度」シリーズ
日本航空(JAL)は公式TikTokで「旅する度」というショートドラマシリーズを公開し、大きな反響を得ました。久米島への旅行中に起こるカップルの日常を描いた共感を誘うPRコンテンツとして、多くの視聴者の心を掴みました。
このシリーズの特徴は、直接的な採用訴求ではなく、JALを利用した旅の魅力や、そこで働くCAの存在を自然な形で印象づけている点です。視聴者は「こんな素敵な場所に人を連れていけるCAという仕事に興味がある」と感じるようになります。
このように、直接的な採用メッセージではなく、「その企業で働くことの魅力」を間接的に伝えるアプローチも効果的です。
製造業のショート動画活用事例
製造業など、一見するとショート動画との相性が良くないと思われる業界でも、効果的な活用事例が増えています。
例えば、製造現場の意外と知られていない技術や工程を紹介する「裏側見せ」型の動画や、製品が実際に使われているシーンを感動的に描く「ユーザーストーリー」型の動画などが人気を集めています。
特に、「こんな会社で働いている人がいるんだ」と視聴者に思わせるような、社員の人間味あふれるエピソードを交えた動画は、BtoB企業の採用においても効果を発揮しています。
製造業が動画を制作するメリットとして、マーケティングや社内外のコミュニケーションにおいて非常に効果的であることが挙げられます。特に複雑な製品や製造プロセスを視覚的に分かりやすく伝えることができ、若い世代へのアピールにも繋がっています。
月々20万円からの採用SNS運用支援サービスとは
「ショート動画の重要性は分かったけど、自社にはそのようなリソースやノウハウがない…」
多くの企業、特にBtoB企業ではこのような悩みを抱えています。そこで注目されているのが、「ショート動画」を中心とした採用SNS運用支援サービスです。
サービスの特徴と提供内容
このサービスは、月額20万円からという料金設定で、BtoB企業を主なターゲットとしています。特に「認知度向上」「採用ブランディング」「リソース不足解消」「若手採用強化」「コスト削減」といった課題を抱える企業に最適なソリューションとして提供されています。
サービス内容には、SNSアカウントの立ち上げから、コンテンツ企画、制作、投稿、分析までの一連のプロセスが含まれており、企業は自社のリソースを最小限に抑えながら、専門的なSNS運用のメリットを享受することができます。

導入企業が得られる5つのメリット
このサービスを導入することで、企業は以下のようなメリットを得ることができます。
- 認知度向上:若年層を中心に企業の認知度を効果的に高められる
- 採用ブランディング:企業の魅力や文化を効果的に発信し、ブランドイメージを構築
- リソース不足解消:専門チームが運用を代行するため、社内リソースを最小限に抑えられる
- 若手採用強化:Z世代やミレニアル世代へのアプローチを強化
- コスト削減:専任担当者を雇用するよりも低コストで専門的な運用が可能
特に注目すべきは、このサービスが単なる採用活動の支援だけでなく、企業ブランディングの強化や、社内の活性化、既存社員のエンゲージメント向上にも寄与する可能性がある点です。
自社の魅力を発信するプロセスを通じて、企業自身が自社の強みや独自性を再確認し、より明確な採用メッセージを構築することにも繋がります。
初期費用20万円が先着5社まで無料になるモニタープラン
現在、このサービスでは初期費用20万円が先着5社まで無料になるモニタープランを提供しています。採用SNSの運用に興味はあるものの、初期投資に踏み切れない企業にとって、この機会は大きなメリットとなるでしょう。
モニタープランでは、通常のサービス内容に加えて、効果検証のためのフィードバックを提供することで、サービスの改善にも貢献できます。
採用SNSのノウハウがない企業や、今後中長期的に採用力を高めたいと考えている企業にとって、このモニタープランは検討する価値のある選択肢と言えるでしょう。
自社で始める採用ショート動画の作り方
外部サービスの活用も一つの選択肢ですが、まずは自社でショート動画の制作に挑戦してみたいという企業も多いでしょう。ここでは、自社で採用ショート動画を作る際のポイントを解説します。
企画立案のコツ
良質なショート動画は、しっかりとした企画から始まります。以下のポイントを押さえて企画を立てましょう。
- ターゲットを明確に:どんな人材に見てほしいのかを具体的にイメージする
- 伝えたいメッセージを絞る:1本の動画で伝えるメッセージは1つに絞ると効果的
- 視聴者の興味を引くフックを考える:冒頭3秒で視聴者の注目を集める要素を盛り込む
- ストーリーラインを設計する:起承転結を意識した展開を考える
特に重要なのは、「なぜこの動画を作るのか」という目的を明確にすることです。単に「みんなが作っているから」ではなく、自社の採用における課題解決にどう繋げるかを考えましょう。
撮影・編集の基本テクニック
高度な機材や技術がなくても、以下のポイントを押さえれば、十分に魅力的なショート動画を制作することができます。
- 安定した撮影:三脚やジンバルを使用して、手ブレを防ぐ
- 適切な照明:自然光を活用するか、簡易的なライトを使用して明るさを確保
- クリアな音声:外部マイクを使用するか、静かな環境で撮影する
- テンポの良い編集:不要な部分をカットし、テンポよく展開する
- 字幕の活用:音声がなくても内容が伝わるよう、要所に字幕を入れる
最近のスマートフォンは高性能なカメラを搭載しているため、専用機材がなくても十分に質の高い映像を撮影できます。また、TikTokやInstagramなどのアプリ内編集機能も充実しているので、専門的な編集ソフトがなくても基本的な編集は可能です。
効果的な投稿・運用戦略
制作したショート動画は、適切な投稿戦略と継続的な運用が重要です。以下のポイントを意識しましょう。
- 適切なプラットフォーム選択:ターゲット層が多く利用するプラットフォームを選ぶ
- 投稿タイミングの最適化:ターゲット層の活動時間帯に合わせて投稿
- ハッシュタグの戦略的活用:関連性の高いハッシュタグを適切に設定
- コメントへの積極的な返信:視聴者とのエンゲージメントを高める
- データ分析と改善:視聴データを分析し、次回の制作に活かす
特に重要なのは継続性です。1本の動画で大きな成果を期待するのではなく、継続的に発信することで、徐々に認知度を高めていくという長期的な視点が必要です。
また、社内の若手社員を巻き込んで制作チームを作ることも効果的です。彼らの視点や感性を取り入れることで、より若年層に響く内容になる可能性が高まります。
採用ショート動画成功のための5つのポイント
最後に、採用ショート動画で成功するための5つの重要ポイントをまとめます。これらを押さえることで、効果的な採用ショート動画の制作・運用が可能になるでしょう。
1. 真実性を大切にする
採用動画において最も重要なのは「真実性」です。実際の職場環境や社員の姿を誠実に伝えることで、入社後のギャップを防ぎ、長期的に活躍できる人材の獲得につながります。
過度に美化された内容は、一時的に応募数を増やせるかもしれませんが、入社後の早期離職リスクを高める可能性があります。自社の強みだけでなく、課題や成長途上の部分も含めた「等身大の姿」を伝えることが、結果的には最も効果的です。
「この会社で本当に働きたい」と思ってもらえるような、リアルな魅力を伝えましょう。
2. 社員を主役にする
採用動画の主役は、実際に働いている社員です。経営者や人事担当者だけでなく、様々な立場の社員が登場することで、多角的な企業の魅力を伝えることができます。
特に、ターゲットとする応募者と近い属性(年齢、経歴など)の社員が登場することで、視聴者は「自分もこの会社で働けるかもしれない」とイメージしやすくなります。
社員のリアルな言葉や表情は、どんな華やかな演出よりも説得力があります。
3. プラットフォーム特性を理解する
各ショート動画プラットフォームには、それぞれ特性があります。例えば、TikTokは若年層へのリーチに強く、トレンドに敏感な層に効果的です。一方、YouTubeショートは幅広い年齢層にリーチでき、検索性も高いという特徴があります。
ターゲットとする層が多く利用するプラットフォームを選び、そのプラットフォームの特性に合わせたコンテンツ設計をすることが重要です。
また、複数のプラットフォームに同じ内容をそのまま投稿するのではなく、各プラットフォームの特性に合わせた最適化(縦横比や尺の調整など)を行うことで、効果を最大化できます。
4. 継続的な発信と改善
ショート動画の効果を最大化するには、継続的な発信が不可欠です。1本の動画で大きな成果を期待するのではなく、定期的に異なる切り口の動画を発信することで、徐々に認知度とエンゲージメントを高めていくことが重要です。
また、各動画の視聴データ(視聴維持率、エンゲージメント率など)を分析し、次回の制作に活かすPDCAサイクルを回すことで、徐々に効果を高めていくことができます。
最初から完璧を目指すのではなく、小さく始めて改善を繰り返すアプローチが効果的です。
5. 採用全体戦略との一貫性
ショート動画は採用活動の一要素に過ぎません。採用サイト、説明会、面接など、採用プロセス全体と一貫したメッセージを発信することが重要です。
ショート動画で伝える企業の魅力や価値観が、他の採用チャネルと矛盾していると、応募者に混乱や不信感を与える可能性があります。
採用全体のブランディング戦略の中で、ショート動画がどのような役割を果たすのかを明確にし、一貫性のあるメッセージを発信しましょう。
まとめ:ショート動画で採用ストーリーテリングを成功させるために
採用市場の競争が激化する中、特に若手人材の獲得においては、従来の採用手法だけでは限界があります。ショート動画を活用したストーリーテリングは、デジタルネイティブな若年層にリーチするための効果的な手段として、今後ますます重要性を増していくでしょう。
本記事で紹介した通り、成功する採用ショート動画には「共感を生むストーリー設計」「視聴者を飽きさせない演出」「拡散を促す仕掛け」という3つの要素が重要です。また、「真実性」「社員の主役化」「プラットフォーム特性の理解」「継続的な発信と改善」「採用全体戦略との一貫性」という5つのポイントを押さえることで、効果的な採用ショート動画の制作・運用が可能になります。
自社でショート動画制作に挑戦する場合も、月々20万円からの採用SNS運用支援サービスを活用する場合も、これらのポイントを意識することで、採用成功の可能性を高めることができるでしょう。
採用活動におけるショート動画の活用は、まだ始まったばかりです。先行して取り組むことで、競合他社との差別化を図り、優秀な人材の獲得につなげることができます。ぜひ、この機会にショート動画を活用した採用ストーリーテリングに挑戦してみてはいかがでしょうか。
より詳しい情報や具体的な支援内容については、以下のリンクから資料をダウンロードいただけます。